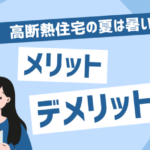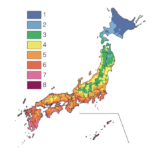HOME BUILDING TIPS お役立ちコラム

大工不足で家が建たない?未来に後悔しない建築会社の選び方
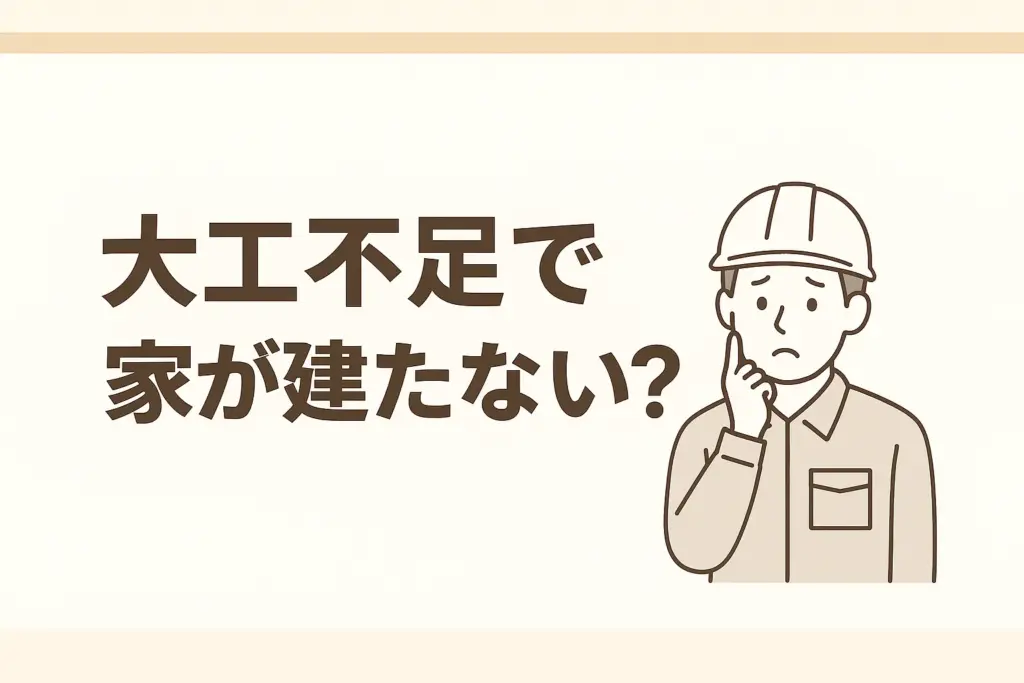
こんにちは。凰建設代表取締役の森です。
人生の多くの時間を過ごす大切な場所、マイホーム。
しかし、その大切な場所を作り出す大工が姿を消しつつあるという深刻な事態をご存知でしょうか?

えっ、大工さんが姿を消している!?家を建てる人がいなくなるってこと?

おうちって、ハウスメーカーさんにお願いすればちゃんと建つものだと思ってたわ…。
二人のように感じる方がほとんどかもしれません。
しかし、この「大工不足」は、これから家を建てようと考えているすべての方に関わる重大な危機なのです。
この記事では、なぜ大工不足が起こっているのか、その原因と、暮らしに与える影響について詳しく解説します。
さらに、本当に信頼できる建築会社を見極める具体的なコツをお伝えします。
これから家づくりを考えている方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
大工不足が引き起こす3つの深刻な危機

大工不足という現実は、具体的に家づくりにどのような影響を及ぼすのでしょうか。
それは、以下のように3つの深刻な危機として現れます。
1.建てたい時に建てられない?リフォームも災害対応も困難に
まず直面するのが、需要に対する大工の数の著しいアンバランスです。
経験豊富なベテランは高齢化し、若者のなり手は激減しています。
その結果、限られた腕の良い大工さんを、多くの建築会社が「取り合い」する状況が生まれています。
これにより、計画通りの工期で家を建てることが難しくなるだけでなく、将来にわたる問題も発生します。
家は建てて終わりではありません。
10年、20年と住み続ける中で必ず必要になるのが、メンテナンスやリフォーム。
その時、頼れる若い大工がいなければ、どうなるでしょうか。
さらに、台風や豪雨といった災害時、迅速に駆けつけられるのは現場を知る大工だけです。
社員大工のいない会社では、緊急時にあなたの家族の安全を守れない可能性があるのです。
2.会社の倒産でアフターサービスが消滅する
大工不足は、建築会社そのものの存続をも脅かします。
特に、職人の育成を怠り、外注に頼りきってきた会社は、人件費の高騰と職人確保の困難化というダブルパンチを受け、経営体力が削られていきます。
もし、あなたの家を建てた会社が倒産・廃業してしまったら、どうなるでしょうか?
約束されていたはずの長期保証やアフターサービスが受けられなくなります。
家の不具合が見つかっても、相談する相手がいなくなります。
長く安心して住み続けるためには、その会社が10年後、20年後も健全に存続しているかという「持続可能性」を見極めることが、何よりも重要なのです。
3.品質の低下と地域社会の衰退が起きる
大工不足と人件費高騰への安易な対策として、業界では建材のユニット化やプレカット化、つまり「現場での手仕事を減らす」流れが加速しています。
これは一見、効率的に見えますが、本来は大工の繊細な技術で調整されるべき部分が簡略化され、住宅の品質管理が二の次になるリスクをはらんでいます。
また、現場での手仕事が減り、全国規模で流通する工業製品に頼ることは、地域にお金が還元されない仕組みを生み出します。
地域の大工や職人に支払われるはずだった人件費が、大資本の本社に吸い上げられてしまうのです。
これは地域の雇用を奪い、職人文化を衰退させ、ひいては地域経済全体を弱らせていく、負のスパイラルに他なりません。
なぜ大工は消えていくの?業界に根付く3つの構造的問題

では、なぜここまで深刻な大工不足に陥ってしまったのでしょうか。
それは、若者に人気がないから、という理由だけではありません。
建築業界そのものが抱える、大工を育て、技術を継承することを阻む、根深い構造的問題が存在するのです。
1.崩壊した「大工育成システム」
大工不足の最大の原因は、職人を育てる仕組みが完全に崩壊してしまったことにあります。
そもそも大工は、数ある建築職種の中でも特に難易度が高く、一人前になるまでに最も時間がかかる仕事です。
見習い期間は、当然ながら生産性が非常に低くなります。

昔の職人さんって、親方のもとで住み込みで働く「丁稚奉公」みたいなイメージがあるなあ。

そうよね、お給料も安くて大変だったって聞くわ。でも、今はそういうわけにはいかないものね。
まさにその通りです。
かつては、その低い生産性のしわ寄せが「低い賃金」という形で本人に来るのが当たり前でした。
しかし、現代の労働基準法のもとでは、そのような働き方は許されません。
見習いであっても、一人前の職人と同様の給与や社会保険を保障する必要があります。
つまり、若手を育成するための経済的な負担が、すべて雇用主である会社にのしかかる構造になっているのです。
これが、多くの企業が育成に二の足を踏む大きな理由です。
2.「傭兵」を雇う方が楽で安いという短絡的な考え方
自社で若手を育成するには、莫大な時間とコスト、そして何より情熱が必要です。
そのため、多くの建築会社は、より簡単で安上がりな方法を選択してしまいます。その根底にあるのは、次のような極めて短絡的な考え方です。
「大工育成なんて、自分の会社の仕事じゃない。どこかの誰かが時間と金をかけて育てた一人前の大工を、必要な時に良い単価で引き抜く方がよっぽど賢い」。
彼らにとってこの考えは、非常に合理的に映ります。
それは、お金のない国が戦争をするなら、自国の兵士を一から育てるよりも即戦力の傭兵を雇う方が安上がりだという理屈と同じです。
あるいは、プロスポーツチームを運営するなら、当たるかどうかわからない博打のような育成にお金を使うより、他のチームで実績を上げた有能な選手に大金を払って引き抜く方がコスパが良いと判断するのと同じことなのです。
私たちはこれを「傭兵的な雇用」と呼んでいます。
このやり方は、短期的には会社の利益になるかもしれません。
しかし、この考え方を建築業界総出で実践した結果、どうなったでしょうか。
誰も兵士を育てなくなった結果、頼みの綱である傭兵すら存在しなくなりつつあるのです。
目先のコストを優先するあまり、自分たちの首を絞め、業界の未来を食いつぶしていることに、多くの会社が気づいていないのです。
3.「まだ大丈夫」という業界全体の無関心
「このままでは大工がいなくなる」という警鐘は、もう何年も前から鳴らされてきました。
しかし、残念ながら、業界全体の反応は鈍いものでした。
「うちは外注だから関係ない」「なんだかんだ言っても、まだ大工はいる」といった短期的な視点と無関心が蔓延し、具体的な対策はほとんど打たれてこなかったのです。
大工を育てるという長期的な投資を怠り、目先の利益を追い求めた結果が、現在の危機的状況を招いています。
大工育成は、業界全体が真摯に向き合うべき構造的な課題といえるでしょう。
大工不足に負けずに建築会社選びを成功させる!施主が持つべき3つの視点

大工不足という厳しい現実を前に、施主は途方に暮れるしかないのでしょうか。
いいえ、決してそんなことはありません。
むしろ、この状況だからこそ、本当に価値のある家づくりを実現するための「正しい会社選びの軸」が明確になります。
ここでは、後悔しないために施主が持つべき3つの重要な視点をご紹介します。
1.「職人を育てているか」が未来への試金石
これからの時代、建築会社を選ぶ上で、最も信頼できる判断基準は「自社で職人を育てているか」という点です。
なぜなら、時間とコストをかけて若手を育成するという行為そのものが、その会社の技術継承への意志、品質への責任感、そして未来を見据えた長期的な経営姿勢の何よりの証明だからです。
職人を大切に育てている会社は、目先の利益に飛びつかず、建てた家とお客様の未来にまで責任を持つ覚悟があります。
それは、将来のメンテナンスや、万が一の災害対応においても安心感につながるでしょう。
2.現代の高性能住宅に応える「知識と技術」の重要性
気密・断熱・耐震など、現代の高性能住宅は、もはや昔ながらの経験や勘だけで建てられるものではありません。
その性能を100%引き出すには、科学的な知識に基づいた、極めて精緻な施工技術が不可欠です。
設計の意図を正確に理解し、現場でそれを高いレベルで実践できる、知識と技術を兼ね備えた大工の存在が、家の品質を決定づけます。
また、出来高払いの歩合給で働く大工は、どうしても品質よりもスピードを優先しがちになるリスクも否めません。
自社で雇用し、じっくりと教育された大工こそが、丁寧で質の高い仕事を実現してくれるのです。
3.会社の「持続可能性」を見極める長期的な目線
家は、ご家族の人生とともに、何十年という時を刻んでいく場所です。
だからこそ、その家を建てた会社も、同じように長く存続する会社でなければなりません。
会社の持続可能性を測る最も分かりやすい指標が「若い技術者の育成」です。
口のうまい営業マンが何人いても、実際に家の不具合を直し、未来のメンテナンスを担うことはできません。
会社の未来を担う若い技術者が活き活きと働いているか。
その会社の「人」を見ることこそが、長期的な安心を手に入れるための鍵となります。
これで安心!「本物の建築会社」を見極める3つの具体的アクション

「大工を育てている会社が良いのはわかった。でも、どうすればそんな会社を見分けられるの?」
当然、そう思われることでしょう。
カタログやホームページだけでは、その会社の本質はなかなか見えません。
しかし、いくつかの具体的なアクションによって、実態を見極めることが可能です。
1.「御社の作業場を見せてください」と聞いてみる
建築会社選びにおいて、非常にシンプルかつ効果的な質問があります。それは「御社の作業場を見せていただけますか?」と尋ねることです。

えっ、そんなこと聞いちゃっていいのかしら?なんだか、あら探しをしているみたいで失礼じゃないかしら…。

でも、本当にいい建築会社さんなら、むしろ喜んで見せてくれるんじゃないかな?自分たちの仕事に誇りを持ってるだろうし!
そのとおりです。
私たちは、この質問を大歓迎します。
木材を刻み、造作材を仕立てる「作業場」は、いわば心臓部。
作業場も持たずに、すべてを丸投げしている会社は、もはや建築会社とは呼べません。
作業場の有無、そしてそこが整理整頓され、職人の情熱が感じられる場所であるかどうか。
それは、その会社の技術力と仕事への姿勢を表しています。
2.営業マンではなく「現場の若手」の存在を確認する
会社の将来性を見極めるには、どんな人材が育っているかを見るのが一番です。
打ち合わせの席で「実際に現場を担当される大工さんは、どのような方ですか?」「若い大工さんもいらっしゃいますか?」と具体的に聞いてみましょう。
もし、ベテラン職人ばかりで後継者がいない、技術継承の仕組みが見えないといった状況であれば、その会社の10年後、20年後は非常に不透明だと言わざるを得ません。
あなたの家のアフターメンテナンスが必要になる頃、その会社は果たして存続しているでしょうか?
3.価格の裏側にある「品質と技術」への対価を理解する
高品質な家を建てるためには、相応のコストがかかります。
特に、私たちの得意とするような、お客様の暮らしに合わせたオーダーメイドの家づくりには、高い技術を持つ職人の丁寧な手仕事が不可欠です。
もし、他社に比べて極端に安い見積もりが出てきた場合は、一度立ち止まって考えてみてください。
その安さの裏には、職人の人件費を過度に削減したり、見えない部分で材料の質を落としたりといった「見えないコストカット」が隠れている可能性があります。
価格だけで判断するのではなく、その価格が「適正な対価」なのかを見極める視点が大切です。
大工不足の時代だからこそ、未来を見据えた会社選びを
今回は「大工不足」という、建築業界、ひいてはこれから家を建てるすべての方に関わる重大な問題について、その本質と対策を掘り下げてきました。
大工不足は、皆様の暮らしの安心・安全、そして大切な財産そのものを脅かす、非常に根深い問題です。
この危機的な状況を生み出したのは、目先のコスト削減を優先し、職人を育てるという未来への投資を怠ってきた業界全体の構造的な欠陥に他なりません。
このような時代だからこそ、施主は、家づくりを託す会社を、これまで以上に慎重にそして本質を見抜く目で選ばなければなりません。
「自社で職人を育てているか?」
この問いこそが、あなたの家と家族の未来を、数十年にわたって守ってくれるパートナーを見つけ出すための、最も重要な羅針盤となるでしょう。
私たち凰建設は「家を作るんじゃない。暮らしを作る」という言葉を胸に、設計から施工、そして未来のメンテナンスまで、自社の職人が責任を持ってお客様の暮らしに寄り添うことをお約束します。
大工育成という、時間もコストもかかる、非効率にも見える道を、私たちは愚直に歩み続けます。
それこそが、お客様へ最高の価値を提供し、未来への責任を果たす唯一の道だと信じているからです。
最後に
今回は大工不足について紹介をしてきましたが、
家づくりにはまだまだたくさんの落とし穴があります。
「家づくりに失敗したなぁ」と思う人を一人でも減らせたらと思い、
ブログではとても書けない事をメルマガで発信しています。
また、メルマガに登録いただいた方には、
特別小冊子「家を建てる前に知らないと大変な事になるお金のはなし」
を特典として無料で差し上げております。
メールアドレスのみで大丈夫です。
下記フォームよりご登録くださいませ。
【実録】建築会社と担当者選びを失敗した理由