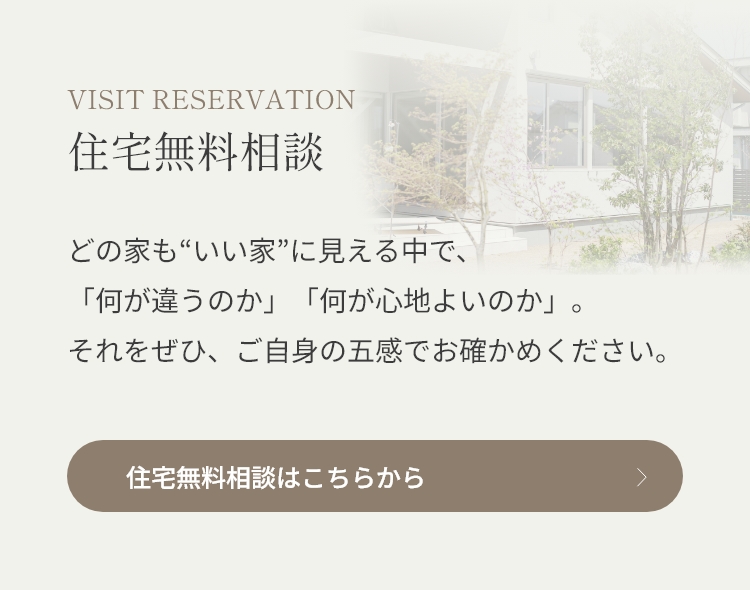QUESTION Q&A

よくある質問
- エアコンの一番おすすめのメーカーと機種を教えてください。
-
毎年色んなメーカーの商品を比較しますが、なかなか難しいですね。というのも、エアコンは「何が最高かよりも何が最適か」だからです。家一軒一軒、最適なものが違いますのでここ最近の引き渡しでも機種は殆どバラバラです。
- 小屋裏エアコンから二階の居室へ冷気を送り込むための設備、設計はどのような点を意識していますか?
-
エアコンから出てくる風量をどの部屋にどれだけ配るかという事がポイントです。配る方法は、換気扇を回すか、冷気の自由落下に任せるかのどちらかです。また、どちらにしても、冷気を配るだけではなく、その元になる空気をどこから持ってくるかも大事です。それも、吹き抜けなどを通して供給するか、ダクトを縦に配管して供給するかになります。
後は、配管をする場合は、それなりの風量になりますので、ファンの音の問題が出てきます。最後に、基本的な事になりますが、空気の熱容量と送風量の計算をしっかりせねば失敗します。
- 以前、分電盤から屋外に配線を行うことができるような予備スリーブ穴をあけて引き渡しされるとのことでしたがそれは気密性が高い物でしょうか?私の家も同じ仕様にしたいので、品名品番を教えて頂きたいです。
-
普通のエアコン用のスリーブになります。
型番までは指定しておりませんでしたが、内外が軽くネジになっており、使わない時は気密が保たれている製品になります。
建築会社に言っていただければわかると思います。
- エアコンのグレードについて、高価格帯と低価格帯ではCOPが2~3異なります。生涯コストで考えると、どちらの方が良いのでしょうか?
-
それぞれの設計士さんの思想によるかと思いますが、私の場合は、更新が必要なものに高価なものはなるべく使わず済む様にしたいという思いから、極力グレードの低いエアコンで済む様に各種の設計を行っております。
家の性能がアンバランスであるほど高性能なエアコンが必要になり、家の性能のバランスが良いほど、低機能なエアコンで済む様になります。
COPは定格域では2~3違ってきますが、低負荷域、高負荷域であればそんなに差がつかないものの方が多いです。
高価格帯なエアコンが将来的に元が取れるかというと、ちょっと厳しいかなぁと思っております。
- エアコンによる除湿を突き詰めていくと、顕熱比はどのくらいまで下げられるのでしょうか?
-
安いエアコンでも瞬間風速的に50%程度まではいけます。
ただ、絶えず50%で動いてくれるかというと、そうでもなく、新しいエアコンほど上手にサボろうとしますので、平均では70%とか80%とかになってしまいます。
うまく空調設計をすることで、少しずつ顕熱比を下げることができるようになります。
これまでにいただいた質問
- COPやAPFが似ている同シリーズのエアコンの6畳用と10畳用、200V 14畳用を同じ条件下において暖房モードで動かした場合、同じ消費電力、吹き出し温度になりますか?エアコン効率や連続運転に14畳用がそもそも向いているのか伺いたいです。
-
6畳用(2.2kW)が400Wの消費電力で動いているという事は、800~1200Wの出力かと思います。
4kWのエアコンに変えても、同様の出力で動かすことはできるかと思いますが、その場合は2.2kWのエアコンの方がCOPは高い状態にあることが多いかと思います。
コンプレッサーの定格容量に近い状態で運転されているからですね。吹出温度については、コンプレッサーが送る冷媒の量などによっても変わりますので、同じとは限りませんが、劇的に変わるものでもありません。連続運転が向いているかどうかは、再頻出の空調負荷が、コンプレッサーの定格容量の2割減くらいに設定できるかどうかになります。14畳用のエアコンと6畳用のエアコンが定格の条件で連続運転した場合、消費電力の差は400W程度になります。暖冷房の時間が年間3000時間あったとすると、1200kWhの消費電力の差、35円/kWhだとすると42000円/年の暖冷房費の差になります。
6畳用が定格条件で連続運転で済むような空調負荷の家を設計した方がやはり有利かと思います。エアコンの選定よりも前に、空調負荷の計算が大事になります。それにより、6畳用の方が効率が上がることもあれば、14畳用の方が良い場合も有ります。
- エアコンのドレンパンのカビが気になります。ドレンパンを銅製にしているものは効果があるのでしょうか?また、このカビが室内の空気汚染につながることはありますか?
-
確かに銅の方が生えにくくはなってきますが、やはりカビは生えます。
効果が高いのは絶えずコンプレッサーが動き続け水が流れ続ける環境を作ってあげる事です。エアコンを24時間回しっぱなしにすればいいかというと、それだけではなく、適切な容量選定と負荷のコントロールが出来ていなくてはなりません。でないと、エアコンがいつの間にか止まっているという事になり、その時間にカビが生えます。皮肉な話ではありますが、お上品なAI搭載高性能防カビ仕様高容量エアコンが発停を繰り返しながら動くよりも、頭の悪い激安低容量エアコンをぶん回すように使った方が絶えず水が流れ続けてくれます。水が流れ続けるという事は除湿効果も高まるという事です。更に、高性能エアコンと激安エアコンですと、初期コストで5~10倍の価格差が発生します。冷暖房費のランニングコストを下げるのはエアコンの仕事ではなく、家の性能の仕事になりますので、十分な家の性能を確保したうえで、激安エアコンを馬車馬のように働かせ、ダメになったら早めの交換というのが比較的カビのリスクの少ないエアコン選定になります。ちなみにエアコンにかかる生涯コストもその方が随分と安く済みます。
- 小屋裏エアコンについてです。階段上部にエアコン本体と同じくらいの面積の吹き抜けがあり、そこから小屋裏エアコンへ吸気しているのですが、エアコン吸い込み口は床下エアコンのように吹き出し側と仕切りを付けて分けた方がいいのでしょうか?
-
エアコンが吹き出した空気が冷たいまま(暖かいまま)エアコンの吸い込み口に戻ってしまうことをショートサーキットと呼びますが、それが起きてしまうと、エアコンは非常に低い効率で動くことになってしまいます。これは冷房でも暖房でも同じことですので、ショートサーキットが起きそうな場合は、仕切りを設けたほうが良いです。
- パッシブハウスオープンウィークスでは空気質のコントロールのためにも薪ストーブを利用されていたと思いますが、冷房期に多くの人が集まるケースではどのような空調コントロールが考えられますか?
-
冷房期の空調コントロールは一般的にエアコン一択だと思います。
家の中で発生したり、外部から入ってくる顕熱潜熱を効果的に打ち消せる容量のエアコンを選定するというのが基本になります。
- 温熱が得意な工務店はエアコン2台で家を涼しく、暖かくしていますが、全部屋にエアコンをつけてでは快適な家は難しいのでしょうか?
-
勿論全部屋に付けても良いですが、全体の容量が大きすぎる計画になりがちで、エアコンの効率が下がって省エネにはならない事も多いです。
また、夏場はその使い方ですと除湿が出来ずに悩むことが多くなります。冬はエアコン1台、夏は負荷の状態に合わせて2台使いというのが、今の所バランスが良いかなと考えております。