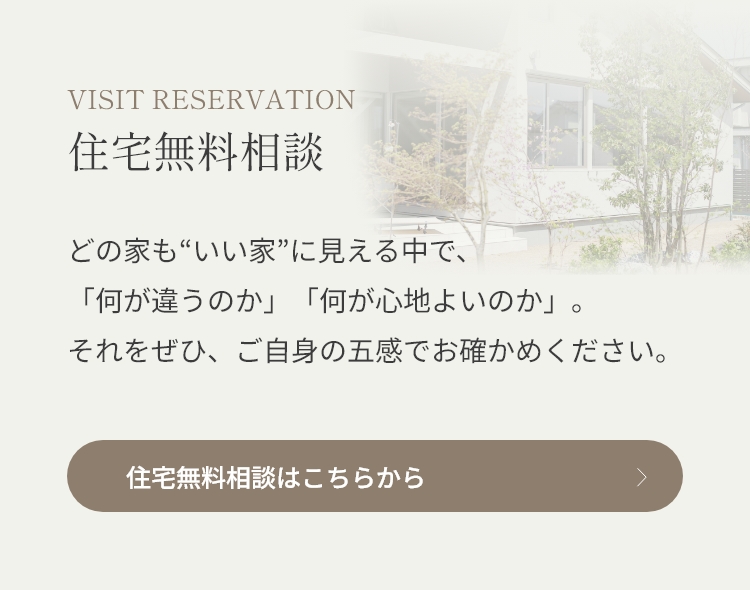QUESTION Q&A

よくある質問
- 凰建設は自社で大工育成をしておりますか?
-
凰建設は1959年の創業時から一貫して新卒大工さんを採用し育成をしている会社となります。
- 新築で気密、断熱、温熱が良かったら家造りは何割成功だとお考えですか?
-
私の主観では3割くらいかと思われます。残りは構造で2割、間取りや設備、耐久性などを合わせると5割位だと思います。
- 長期優良住宅認定と性能評価認定は取得していますか?
-
長期優良住宅と建設性能評価は標準で全棟採用しております。
- 土地探しからスタートする場合、どのような流れで進めていますか?プランが分からない段階で土地を購入するのが心配です。
-
土地が決まらないとプランを出すことは難しいですが、要望のヒアリングは、必ず土地を決める前にさせていただくようにしておりますのと、土地を決める最終決定の前には、私も土地を見させていただくようにしております。その土地で要望が全部収まりそうかどうかを自分で検討してから、「買ってもいいと思いますよ」とお伝えするようにしております。
- 土地選びにおいて重視していること、外せないことはありますでしょうか。
-
災害リスク、人口が減少していないことは気にしておかなければなりません。
またもう一つの観点として、将来的に自分が管理すべき不動産を増やさないという事です。両親祖父母は勿論、親戚筋から、将来自分が相続することになりそうな土地がある場合は要注意です。
核家族化少子化が進み、思わぬところから土地や建物を相続することも起こっております。そのような土地がある場合は、今の時点で新たに不動産を購入することはよくよく検討した方が良いです。その土地に家を建てたほうが、何年か待ったとしても生涯で家や土地に使うお金は少なくて済むことが多いです。
- 伊勢湾台風以来1度も水害が無い、伊勢湾や長良川に近い1種低層エリアでは新築しない方が良いですか?
-
長島-桑名-四日市あたりの場合、台風もですが、地震による地盤の崩れや津波の方が心配かなと想像致しました。
ハザードマップをよく確認していただければと思います。
- 候補の土地から50mのところに電話会社の鉄塔があります。ネットで電磁波で健康被害が出ると記事がありましたが、どのようにお考えですか?また、電磁波を防ぐ方法はありますか?
-
GHz帯の電波の場合、電波防護指針の基準値は61.4V/mという電界強度以下が求められます。デジタル携帯電話基地局のアンテナ基地局から発せられる対象とする空間における電界強度は50m地点であれば0.5V/m前後であることが多いと言われています。
それでも気になるようであれば、電磁波をはじく目的で、基地局アンテナ方向の屋根や壁面にアルミを蒸着させた遮熱シートなどを施工すると良いかと思います。窓はブルーやブロンズのLow-Eガラスにした方が良いかと思います。
ちなみに、一般的なノートパソコンから発せられるゼロ距離の電界強度は1500V/m前後になります。
電磁波が気になるようであれば、家の外からやってくる電磁波よりも、家の中で発生する電磁波の対策が優先かと思います。
- 自己資金はどれくらい必要ですか?
-
設計申込の際に50万円(税抜)をお預かりします。住宅ローンを組むには自己資金が1割程度は必要だと言われますが、資金についてのご相談も無料住宅相談で承っております。
お申し込みはこちら→https://www.ohtori.net/reserve/
- 坪単価って何ですか?
-
坪単価とは、家を建てるときの1坪当たりの建築費のことです。建物の本体価格を延べ床面積(坪)で割った数値のことです。1坪はおよそ3.3m²で、家を建てる時のおおよその目安として一般的に参考にされています。例えば延床面積30坪の家が2400万円だとしたら、坪単価は80万円ということになります。
- 予算の中に工務店さんへお支払する設計費用・構造計算費用・長期優良住宅申請費用・確認申請費用・完了検査申請費用・設計監理費用があると思いますがいくらぐらい見込んでおく必要があるのでしょうか?
-
設計事務所さんですと、工事費の1割程度が目安になります。
工務店だとその半分くらいかなと思いますが、工務店の場合は工事費の利益の中に設計費用を分散して入れ込んでしまい、設計費用という項目を殆ど計上しないということもできますので、実態はバラバラだと思います。
現実的に会社の原価から計算すると、依頼する工務店の設計士さんと会った時間×2万円+各種申請の実費くらいは会っていない時の作業も含めて掛かっておりますので、私は掛かっている費用を素直に見積もりに計上した方が、後々辻褄の合わないことが起こりにくくて良いのではと思っております。
- 見積りはどの段階でいただけますか?
-
資金計画はご相談段階で無料で行っています。ヒアリングをした上で、家を建てるのにかかる金額、家を建てた後にかかる光熱費、メンテナンス費、経費など全てひっくるめた総額をご提示しています。詳細なお見積りについては、設計申し込みを頂いておおよその図面が確定してからお作りしております。
- 使用部材によると思いますが、生涯コストの目安となる金額はどのように算定すればよろしいでしょうか?
-
日本の家の実績値として、税金、メンテ、光熱費、保険等々含む年間約60万円の維持費がかかります。
60年住むと約3600万円のお金がイニシャルコスト以外にかかってくる計算になります。税金・保険はあまり変えようがありませんので、メンテ費や光熱費について、しっかり設計者さんに積算してもらうと良いです。JBNさんがメンテ費の計算シートなどを配布しておりますので、そういったものを利用するか、ebifitという私どもが作った生涯コストシミュレーターを使っている設計者さんを探してください。
- 地盤調査について、スウェーデン式サウンディング試験と表面探査ではどんなメリットデメリットがありますか?
-
表面波探査法の方が地盤に対してより包括的な調査を行えますので、地盤の全体像が把握しやすいです。
結果、スウェーデンサウンディングで、たまたま弱い部分を調査してしまったが為に本来やらなくても良い改良が発生してしまったなどという確率は下がっていきます。
注意事項としては、表面波探査の方法では、地盤に対しておおよそ15m程度下までしか測定することが出来ませんので、あまりにも軟弱な地盤ですと、改めてスウェーデンサウンディングを行わなければならないという事もあったりします。
- 氷点下になりそうなタイミングで基礎工事の予定がある場合、コンクリート打設はそのまま実施されるのでしょうか?
-
打った翌朝の気温が0℃を下回ると、少し心配になります。基本的には打ったコンクリートがきちんと保温されている状態であれば、大丈夫です。コンクリート自体は固まる際に水和熱を発生させますので、それが逃げて行かないように、木製型枠を使ったり毛布をかけたりして、保温します。養生中のコンクリートの温度が5℃を下回らないようにというのが目安です。AE材の使用や温度補正も気温に応じて行います。
- 基礎の二度打ちは一体打ちより強度が下がるので一体打ちは当然。みたいな動画を見たのですが、基礎の一体打ちは耐震等級3と同等に必須なものなのでしょうか?
-
私はどちらでも構わないと思っております。
打ち継ぎができない分構造は一体化しますが、天端の精度が落ちがちなので、気密性のためには2回打ちの方が良かったりもします。RCの現場であれば各層ごとに打ち継いでいきますので。
立ち上がりと地中梁が両方ある場合などは、梁の中で打ち継ぎが発生することになりますので、1回打ちの方がいいかなと思ったりします。
何が何でも1回打ちじゃないとダメという事は有りませんので1回打ち、2回打ち、どちらの場合でも、それぞれのやり方に応じた丁寧な施工をしてもらえるといいと思います。
- 床下自主点検のために基礎の高さは何センチ以上必要でしょうか?
-
長期優良住宅のルール上は床下の空間は有効で300mmの高さが必要となっております。しかし、住まい手の方が自主点検で潜るとなった場合、体格によっては300mmでは通れないという事も発生致します。床下をしっかりと点検できるものにしようと思うと、有効で600mm程度(ダイニングテーブルの下の空間くらいの高さ)があった方が良いです。しかし、今の日本の家づくりでそこまでの空間を作る事は、非常に稀です。
将来的には床下空間の高さもどんどん高くなっていくのではと想像しております。
- 基礎内断熱で床下の換気を考える場合にガラリをつけない換気以外はどのような方法があるでしょうか?例えば、床下エアコンや第一種換気でも十分できたりしますでしょうか?
-
ガラリを無くして施工したこともあります。築後数年はマメに点検しましたが問題は発生しませんでした。防湿の設計施工がしっかり出来ていれば、床ガラリの無い基礎断熱でも大事故が起きる事はありません。しかし、全ての家でお勧めできる仕様ではありませんので、ガラリを付けておいた方が無難だとは思います。あえてリスクを抱える必要もないかと思います。
床下エアコンを設置する場合、吹き出し口になるガラリを通って温風が循環しますので、ガラリ無しはあまりお勧めできません。第一種換気の給気や排気を床下に設置する方法であれば、そこまで問題はありませんが、床面や間仕切り壁から床下への給気が全くない施工をしてしまうと、予定通り換気できていないという事も起こりえますので気をつけてください。
設計者さんによく相談されると良いと思います。
- 木材の含水率は何%くらいであればシロアリ対策には安心でしょうか?
-
20%は切っておきたいです。できれば15%以下が望ましいです。木材が白蟻にやられる理由は、施工時に湿っているというよりも、施工後も継続的に湿り続ける事が原因です。きちんと木材が乾く施工になっているか、水分の供給源が無いか(結露や雨漏り)がものすごく大事になってきます。
だから、高気密高断熱が必要になってきます。
- 新築で白アリ対策は加圧かホウ酸か何が良いかご提案ください。
-
ものすごく沢山の考え方があり一概には言えませんが、各種論文を読み解く限りでは、日本の岐阜において最も永続的に効果のあるシロアリ対策は、木材の乾燥状態を保つことになります。
勿論薬剤を使っても良いとは思います。じゃあ、木材の乾燥状態を保つためにどういう工夫をして、どういう効果が見込めて、その時のシミュレーションは妥当かどうかという検証をすることは誰もやらないので、結局保証のある薬剤に頼るしかなくなります。
自信が無ければ強い保証の薬剤に。自信があれば弱い保証の薬剤に。
だから、その建築会社さんがお勧めする物が、その建築会社さんで建てるのであれば最も良いものになるはずです。
一概には言えません。何が良いかではなく、あなたの場合に何が「最適か」で決まります。
- アメリカカンザイシロアリの被害が拡大している様ですが、新築時に何か対策をされていますか?
-
これは厄介な問題ですね。
現在の所、気にされる方は全棟ホウ酸処理を勧めるという形になります。
建物を建てる際には様々なリスクを天秤にかけて予算の使い方を決めますが、質問者さんにとって、カンザイシロアリのリスクがどの順位に来るかによって、予算が回る/回らないを決められたら良いかと思います。
恐らく日本で一番白蟻の事を研究している京都大学の吉村教授は、外来種であるカンザイシロアリの対策は、根絶させる事であり、地域自治体全体で取り組まなくてはならないと言われております。マクロな話をすると、これ以上アメリカから木材や古家具を輸入しないというのが、最も現実的な対策になります。つまり、国産の木材を使って家を建てるという事が、まわりまわってカンザイシロアリの撲滅につながります。
- 基礎外断熱に使用する防蟻断熱材のおすすめを教えてください。それに付随して、土台までのルートを塞ぐ専用テープなどの役物系のおすすめも教えていただけると助かります。
-
熱橋にはなりますが、コンクリートから基礎外断熱までを金属(やアリダンテープ等)で囲い、木部と縁を切ることをお勧めしております。
防蟻断熱材はどちらでも良いかと思います。
- シロアリ対策で重要なのは乾燥や日頃の確認だと思いますが、第二第三の策として家全体のホウ酸処理やacq加圧注入材などもあるかと思います。これらに森さんはあまり積極的ではないのは理由があるのでしょうか?
-
床下を屋内空間として使いたいからです。
床下がカラッカラに乾く高気密高断熱の家(床下熱源なら尚更)はヤマトシロアリ、イエシロアリに対して非常に効果の高い防蟻効果を出しますが、床下空間が薬剤にまみれた木材で構成されていると、その空間は果たして綺麗か?という懸念が残ります。とはいえ、あまり大きなこだわりというわけでもないので、ホウ酸も注入材も希望があれば使います。
- 凰建設で建築した場合、構造計算の計算書を頂くことは可能でしょうか。
-
はい、可能です。構造計算や断熱計算など、全ての書類は引き渡し時に住まい手にお渡ししております。許容応力度計算の書式などは数百ページに及びますので、けっこう嵩張ります。しっかり保管していただければと思います。
- 凰建設では柱直下率に基準を設けていますでしょうか?
-
柱単体というよりも、耐力壁としての直下率を50%以上にするという社内基準を設けております。ただし、これは最低限の基準ですので、より上を目指すに越したことはないと思います。
- 許容応力度計算をしている耐震等級3と、していない耐震等級3ではどのような部分で違いは出ますか?
-
同じ耐震等級3というランク付けになりますが、許容応力度計算で求められている強度の方が、品確法による耐震等級3よりも強い為、許容応力度計算を行ったうえでの耐震等級3の方が地震に対しては強い建物になります。許容応力度計算と品確法の性能表示における計算の大きな違いは、偏芯率の算出、部材一本一本の断面、接合部検討になります。
ちなみに、許容応力度計算が最高の構造計算方法だと思われがちですが、建築の世界には、更にその上に「限界耐力計算」「時刻歴応答解析法」という、部材が破断するまでの強度を計算して、建物の限界を算出したり、地震波に対して、各接合部がどの様に挙動するのかをも考慮して耐震設計をする方法があります。
巷で話題のウォールスタッドというソフトは時刻歴応答解析法の結果を分かりやすく可視化したものになります。
- 地震に強くするには、耐震等級3と筋交いと制震ダンパーですか?面材は不要ですか?
-
外壁面の面材は必須です。耐震等級はどちらでも取れますが、断熱施工的に外周部に筋交いがあると大変です。できれば面材で6面囲うような家が丈夫ですね。
- 制震ダンパーの費用対効果をどうみますか?
-
制振ダンパーの費用対効果は難しいです。
というのは、各種耐震関係の部材というのは、毎年確実に効果の出る断熱とは違い、地震が来なければ、建物の一生のうち、一度も使われずに終わる可能性もあるからです。
大地震に見舞われることなくその生涯を終える古民家もよくあります。耐震制振免震の部材選定については、「保険」のレベル設定だと解釈をしていただいた方が良いかもしれません。
どこまでを想定して建物の強度を担保しておくか。当然強い保険(等級3+制振)をかけておいた方が何かがあった時にも安心と言えます。制振部材にはダンパー系、テープ系などがありますが、少し気をつけた方が良いのが、最初から制振部材として効くものなのか、それとも最初は耐震部材として働き、耐震部材として限界を迎えてから制振部材として効くものなのかということです。
どちらかと言えば最初から制振部材として働くものを選んだ方が、家全体として、耐震部材の痛みを防いでくれるようです。費用対効果というテーマではお応え出来ておりませんが、制振部材についてはこのように考えております。
- 気密性能ですが、最低でもC値1.0がよいと言われる方が多いと思いますが、30年〜50年後でも同じ気密性能を保てるのでしょうか?もし三種換気などで気密性能が落ちてしまうと当初の換気計画通りにならなくなるかと思います。また、気密を落とさない工夫や落ちた場合の対処方法はありますか?
-
気密性を落とさないためにはいくつかの方法が有効です。
まず耐震性能を上げる事です。家を固く作り、細かい地震ではびくともしないような構造にしておくことで、気密性能の低下は防ぐことが出来ます。
次に外張り断熱を併用する事です。構造材の収縮も気密性を落とす大きな要因ですが、外張り断熱の家の場合は温度変化による木材の収縮を大きく減らすことが出来ますので、気密性能の劣化は少ないです。
次に含水率の低い木材を使う事です。施工後に木材が痩せるのを防ぐことが出来ます。
最後に、細かい振動から有効な制振材を使う事です。大地震の時だけではなく、小さな地震から効果を発揮する制振材を使う事により、構造の変位を抑える事が出来ますので、結果として気密性能が落ちにくくなります。
気密性能が経年によりどの程度落ちるか、どんな原因で落ちるかという事は1990年には既に北海道工業大学の研究室にて実測された研究結果が論文発表されております。
上記の対策を全て講じた場合、気密性能の低下はほぼ発生しないと思っていただいて大丈夫です。
- 気密テープは地震で剥がれたり破れたりしないんでしょうか?
-
構造が柔らかいと破れます。なので、耐震等級3の硬い構造と高気密高断熱はセットで必須なんです。
- かなりの虫嫌いなのですが、気密がいいとゴキブリなどの虫が入り込むこともほとんどないと考えてよいのでしょうか?
-
家にある隙間の形状が該当する虫よりも小さければ物理的に虫は入ってきません。
玄関ドア下枠、引き違いサッシ、サッシの水抜き穴、エアコンのドレンホースが高気密住宅の代表的な侵入経路ですが、それに加えて田舎だと野菜をもらってきたときの段ボールも侵入経路として挙げられます。
- 新築で気密シートを施工して貰う予定なのですがエアコンの据付板を取り付ける時にせっかく丁寧に貼った気密シートに穴を空けてしまうことになってしまいそうです。対策とかあるのでしょうか?
-
そういう事が起こらないようにするためにも、配線胴縁を施工しておくことをお勧めしております。
下地を気密シートの内側に取り付けてもらうというのがまさにそれです。
高気密高断熱のエアコンを理解している人に施工してもらえるように頼んでいただければと思います。
- YouTubeなどで床下点検口のカバーが浮いている動画があったりします。どのぐらいの気密性があれば、このような現象が起きるのでしょうか?
-
内外圧力差が点検口の重さや止めつける力を上回ればそうなります。例えば40Pa(N/m2)の圧力差が生まれ、50cm×50cm(0.25m2)
の蓋を持ち上げようとしたとすると10N(約1kg)の浮力がかかることになります。
内外圧力差(Pa)×点検口面積(m2)×0.102(kgf/N)で浮力が算出されます。
浮力が蓋の重さの半分を超えれば、そういう現象が現れることもあるかもしれませんね。
建築のプロというよりも、普通に物理がわかる方であれば計算できるものかなと思います。
- これから住むのが30年以内ならG1がコスパ的にもベストとお聞きしましたが、ランニングコストの面からみても、少し無理をしてG2グレードにしておくのはやはり無駄なのでしょうか?
-
30年以内なら生涯コスト的にG1がベストというのはその通りですが、あなたが建てた家はあなたが亡くなられた後はどうなりますでしょうか。
戦争が終わって以降、日本人は自分の事だけを考えて家を作ってきました。その結果が今の空き家問題です。G1に満たない家を作るよりははるかに良い事だとは思いますが、自分の家を受け継いで住む人たちの事を考えてみるのはいかがでしょうか。
また、G1でいいやという家にしますと、水回りの窓が割と高い確率で結露致します。樹脂窓を使わなくても建てられるからです。
毎日の生活の豊かさはG1とG2、またそれ以上になった場合も全然違ってきます。昨日も兄弟で集まり、等級4の家に住んでいる人、G1くらいの家に住んでいる人、G2くらいの家に住んでいる人、G3くらいの家に住んでいる人が家に対する感想を言い合いましたが、この時期の寒さに対する感想は全く違っていました。
- 天井の断熱性能(部材、厚さ)の標準はどれくらいですか?
-
物件によってバラバラですので標準の断熱性能というのはありませんが
現在進行中の現場ですと、R値6.3㎡K/W(高性能グラスウール16Kで240mm相当)が最低で、R値15㎡K/W(高性能グラスウール16Kで570mm相当)というのが最高です。住まい手が求める広さ、温熱環境、冷暖房費、生活スタイルから性能を逆算して決めております。あなたがこうありたいと願う暮らしを実現させるために必要な断熱の厚みを提供します。
- 高気密高断熱住宅は乾燥すると聞くのですがなぜでしょうか。一般住宅との違いを教えて頂きたいです。
-
一般住宅よりも同じ暮らしをしていても温度が上がるからです。温度が上がれば相対湿度は下がりますので、乾燥している様に感じます。
それだけの理屈になります。
- 現在、家づくり検討中です。その中で付加断熱をしたいと考えてるのですが、付加断熱材でおすすめなどありますでしょうか?付加断熱も充填断熱同様、施工性や施工工務店で使い慣れているものやコスパで考えればいいのでしょうか?
-
断熱材の選定ポイントは、地域の特性に合っているか、やりたい生活に合っているか、土地の状況に適っているかで決めておりますが、その工務店さんの得意なものがあれば、それでお願いしても良いかと思います。
火事が心配な地域なら火を通しにくい断熱材が良いでしょうし、水害が想定される地域なら発泡系の方が復旧は早いです。ケースバイケースで、弊社も使い分けております
- 凰建設では準防火地域の家を建てる際にも、HEAT20のG3クラスの家を建てるのが最終的に最も良いと考えられているのでしょうか?一番性能の良いトリプル樹脂や高気密高断熱の玄関ドアを使用すると防火性能が落ちるため、屋根・壁・床の断熱性能を上げてカバーするのでしょうか?
-
難しい問題ですね。準防火地域では弊社の場合ですと、外側に防火サッシ、内側には内窓という形で性能を上げていくことが多いです。そうすると特に無理なくG3クラスの家は建てられます。
それも人それぞれだとは思いますので、性能を決める際は、どんなところが落としどころになるのかを、住まい手さんとディスカッションしながら決めております。
準防火地域でUA値0.19W/m2・Kみたいな事に落ち着く家もあれば、0.4W/m2・K程度になることもあります。
- 耐久性の高いものと低いものを混ぜないというのは、建築のプロとしては当たり前のことなのでしょうか?それとも凰建設様が独自で取り組んでおられることなのでしょうか?
-
耐久性の高い物と低い物を混ぜないのは日本の家の9割以上が出来ていない事になります。どんな大手ハウスメーカーでも、断熱材、電気配線、水道配管、冷媒配管、換気ダクトなどがごちゃ混ぜに施工されている例は枚挙に暇がありません。折角丁寧に施工された断熱材が一生モノではなくなってしまうのが日本の殆どの家づくりにおいて起きている問題になります。とは言え、同じ問題意識を持って施工している工務店は数は少ないですが全国に沢山あります。決してすごく特殊で技術のいるものではありません。
- 配線の耐久性について質問です。配線の安全性を重視するとおおよそ何年後くらいに交換が必要になりますか?また、配線のメンテナンス性を考えた場合、どのような設計をすればいいでしょうか?
-
電線の直線部分でトラブルが起きる可能性はそこまで高くなく、どちらかというと結束部分です。
断熱材や配線をすべて交換する作業は、新築と同等の作業になり費用も建て替えよりちょっと安い程度の大規模なメンテナンスになってしまいますので、お勧めしておりません。
そのため、断熱材も電線もそのまま埋め殺して、室内にもう一層、配線層を作るというのが落としどころだと考えております。
- メンテナンスを考えた際、貴社では屋根のルーフィングはどのような提案をされますか?またそれによるコスト増はどうなりますでしょうか?
-
基本的にゴムアスファルト系の物を勧めておりますが、これも屋根材との相性によって変わってきます。
ルーフィングそのものも大事ですが、合板の下に風を通す事も非常に大事で、色々な要素が複合されてきますので、建物の計画によるとしか言えません。
良い物を使えば当然コストは上がりますが、屋根材を一度葺き替えることに比べれば、全く大した金額ではありません。
- 壁内の結露、カビ対策について伺いたいです。冬は室内からの湿気を壁内に入れないようしっかり気密をとるのが基本だと思いますが、夏に関してはどうすればいいのでしょうか?夏は外の方が湿度が高いのでエアコンにより室内が冷やされた場合、壁内で一番室内に近い部分が結露してしまうのでないか心配しています。
-
夏型結露の心配ですね。心配されるお気持ちは大変理解できます。理論上、夏型結露は発生し得るものですから。
例えば、夕立が有ったりすると、コンビニの窓ガラスが曇ったりします。車の運転中、冷房をダッシュボードから吹き出す設定にすると、フロントガラスの外側が結露を起こします。
これが生活するうえで身近に起こる夏型結露ですね。では、これが家の壁の中で起こりえるのかどうかという事について考えてみたいと思います。
夏の冷房時の室内温度が例えば26℃だとします。壁内で一番室内に近い側が、そのまま26℃になったと考えますと、その時の飽和水蒸気量は21.35g/kgです。この、21.35g/kgという水蒸気量になるタイミングは、一年でどのくらいあるのかという話ですが、2019年の岐阜県岐阜市の夏の実績ですと、8/16の午前10時から正午までの2時間だけ、この値を超えております。
夏は湿気が高いのは事実なのですが、住宅で常識の範囲内でエアコンの温度設定をして生活をしている限りでは、壁体内の夏型結露というのはそんなに発生しないというのが答えになります。結露を起こすかどうかは、絶対湿度に対して露点温度を下回れば結露するという単純な物理の話です。
夏の結露でもっと心配なのは、明け方の放射冷却によっておこる自然結露です。草に朝露が付いたり、朝靄が発生したりというのもこの現象が手伝っております。
住宅で言えば、屋根の裏側などでこのような現象が起こる可能性があります。これを防ぐためにはやっぱり家に断熱を施し、家中のあらゆる箇所がどんな季節でも露点温度以下にならないようにするというのが最も効果的な対策になります。
調湿気密シートを使ったりという対策もよくなされますが、そんなことよりも、真っ向から断熱に取り組むほうが先です。ヨーロッパ北米並みの断熱をして初めて、調湿気密シートを考え始めましょう。
- 可変調湿気密シートの長期耐久性ってどうなのでしょうか?そもそも、気密シート無しでも内部結露しない壁構成が必須のように思えるのですが。
-
こちらは、私も同様の問題意識は持っておりますが、現状では分からないというのが正直なところです。一般的に物質の劣化原因は、熱、水、紫外線になりますが、そのうちの熱と紫外線から守られているのが気密シートの施工位置になります。残りの、水による劣化がどの程度なのかは耐久性試験の結果からも分かりにくい商品が多く、ひょっとするとやはり30年に1度はめくらないとダメな物かもしれません。
- 窓の日射遮蔽の方法について質問です。これから新築する我が家は、6地域でHEAT20のG2くらいの仕様かつ東道路、南は隣家と3mほど空いています。夏の日射遮蔽にすだれを使おうと思っているのですが、二階の南窓・東窓は滑り出し窓ですだれやシェードがとりつきません。窓の大きさは700×900で南は少し軒が出ています。どうやって日射遮蔽するのがいいのでしょうか?
-
南は軒をなるべく出す、東西は窓をなるべく減らすというのが、2階の日射遮蔽は有効です(角度があまり振れていない場合)
それができないのであれば、せめて反射率の高いカーテンなどを取り付ける事になりますが、内側で出来る日射遮蔽対策は大して効果はありませんので、気休めくらいに思ってください。
- リビングダイニングなどに掃き出し窓を設計することがあると思います。この場合、25120の掃き出し窓は、2枚のものと4枚のものがあると思うのですが、4枚のもので設計することはありますでしょうか?
-
現在施工中の家で、25622−4という、4枚引き違いの掃き出し窓を採用している家があります。理由としては、既に車椅子の生活をしており、庭のデッキから車椅子で出入りする必要があるためです。2枚引き違いでも開口幅は大して変わりませんが、開口位置の自由度が高くなる4枚引き違いを採用いたしました。当然気密の数字は悪くなるはずですので、大工さんにお願いした性能は、いつもの数字(αA)+5cm2です。何を優先するかで、色々な仕様は変わって良いと思います。
- 窓ガラスの色について質問です。ブロンズなどの色ガラスや曇りガラスはプライバシー的には良さそうですが、日射等の影響はどうなのでしょうか?森さんはいつもクリアガラスをご使用でしょうか?
-
南側はクリア、その他の面はグリーンやブロンズです。(ブロンズは北海道限定だと思います。質問者さんは北海道での計画でしょうか?)
ブロンズだと思いっきりガラスのイメージが変わりますので悩ましいところですが、グリーンやブルーならそこまで影響しませんので、気になるならそういう選択肢もあるかと思います。
- 現在APW330(low-e、アルミスペーサー、アルゴンガス入)の引き違い窓の気密向上を目的として内窓の設置を検討しております。気密向上を目的とした場合でも複層ガラスの内窓を選択した方がいいでしょうか?
-
コスパを考えるととりあえず複層を選んでおいた方が良いかと思います。
- 窓について質問です。6地域でUA値0.3くらいの建物で十分な日射が得られると仮定した場合、南面の窓を日射遮蔽型にすることはありますか?日射遮蔽型で熱が逃げる量を抑えることでオーバーヒートも抑えた方が温度一定で快適性が得られる気がしますがどうなんでしょうか?
-
日射取得型でオーバーヒートを起こさないように窓の面積を調整すればよいかと思いますが、あえて大きな窓を施工しておき、日射遮蔽型というのも決してダメではありません。肝心なのは、それをちゃんと計算して狙ってやってもらえるかどうかだと思います。
きちんと計算した場合、コスパが良いのは取得型になります。
- 第3種換気を検討しています。静圧等の圧力制御の性能はどの程度を考慮する必要がありますか?その他スペックで確認した方が良い項目も教えていただければ幸いです。
-
換気扇の静圧はこだわった方が良いのですが、断熱の方がまずは優先ですし、これは住まい手はおろか、ほぼ全ての設計者はどのように数値を確認して設計に生かしてよいかは分かりません。換気扇の静圧で商品を選んでいる人は1000人に1人程度の割合じゃないでしょうか。
まずはしっかり気密が取れている事、暖房時の室内の圧力分布を計算してある事、換気扇の適切な流量が計算されている事が、設計時の確認項目です。
そして、住んだ後に、概ね1000ppm以下のCO2濃度でちゃんと暮らせているかというのがものすごく大事な確認項目です。設計がいい加減でも、住んだ後のCO2濃度がちゃんとしていればそれで大丈夫です。
- 国産の3種換気の選定で将来のメンテナンスを含めて考慮すべき点はありますか?
-
普通のパイプファンであれば後々でも交換するだけで終わりますので、メンテナンス性は気にすることはありません。
ダクト式の場合は、機器本体の交換が発生しますので、必ず機器本体+αのスペースが必要になります。それが無ければ、使い捨てのつもりで採用した方が良いです。
- 中華料理屋で炒め物を週4ぐらい作ってますが、掃除を怠ると煙や油汚れはどうしても発生します。御社のような高気密高断熱住宅の、キッチン周りの間取り、換気設計、キッチンとリビングの設計の考え方を教えていただけますか。
-
その使い方でしたら、必須になるのはキッチンの換気扇は外壁面にくっついている事です。コンロ周りに勝手口や窓は無い方が無難です。オープンキッチンでも良いですが、せめて正面と側面に壁のあるキッチンにすると良いかと思います。換気扇はお掃除機能付きなどは採用せず、掃除のしやすさの1点に絞って探すと良いかと思います。タカラのホーローレンジフードなどは相性が良いかと思います。
- 第一種換気で全熱式を採用する場合、たばこの匂いは家中に広がってしまいますか?
-
また、煙草のヤニの成分などはてきめんに熱交換素子を詰まらせますので、メンテナンスの頻度はかなり高くなります。
家の中で煙草を吸うのであれば、熱交換換気やダクト式の空調は全くお勧めできません。普通の第三種換気にしておいて、吸排気のフィルターをマメに変えたほうが良いです。
- 一種のダクト式換気で、OAに電子集塵機をつけている事例を見かけるのですが、集塵機があるとダクト清掃や熱交換素子交換の頻度は下がるものですか?
-
はい、下がりますね。ただし、電子集塵機の本当に必要な地域なのかどうかはちょっと考えてみてください。
田舎の空気が綺麗なところであれば普通のフィルターで十分ということもありますので。
- 高気密高断熱、可能ならパッシブハウスに近づけたいのですが、予算が足りないのかなと不安です。高気密高断熱はそのままで、価格を抑えることも可能なのでしょうか?その場合のデメリットはありますか?
-
高気密高断熱をそのままに価格を抑える事は可能です。ただし、何もデメリットなく抑える方法はありません。建物の予算をどのように配分するかという事だけになります。
予算の掛け方は、大きさ(坪数)構造(耐震)性能(断熱気密)耐久(防水防蟻排湿)意匠(デザイン)内装(床壁天井)設備(キッチンバストイレ照明IOT他)外装(屋根外壁樋)埋設設備(配管配線)に分けられます。限られた予算の中で、性能に対するお金の掛け方を増やしたければ、その他の予算を削ることでパッシブハウスクラスの断熱性能を持つ家にすることは十分に可能です。
ここで気を付けたいのが、削る順番を間違えると何も意味が無いという事でして、高性能な住宅は長い年月の中で最も温熱環境的にも経済的にも優れたものを目指したものになります。1年しか住まない仮の家なら沢山の冷暖房設備を入れたほうが快適で安いです。
という事で、長く住む為の要素を削ると意味が無くなってしまいます。具体的には構造、耐久、埋設設備、外装です。長い年月の間に地震で痛んでしまうと高気密の性能も台無しです。排湿が上手くできずに腐ったりしてしまうとやはり台無し、外装の耐久性が悪くメンテが追いつかずに雨漏りをしてしまっても台無し、電気配線のメンテのタイミングで断熱をめくらないといけないような家でも台無しです。
それ以外の要素は後からでもやり直しはできます。
という事で予算が足りない場合、パッシブハウスクラスの物にするためには、広さ、設備、意匠、内装の順に予算をカットしていく事になるというのがデメリットでしょうか。
ちなみに、弊社の場合、構造、耐久、埋設設備に関しては、削るという選択はしませんので、性能、大きさ、外装、設備、意匠、内装の天秤で、予算を決めていく形になります。
- 土地は探してもらえますか?
-
ご希望であれば、不動産部門の担当が土地探しから買付けまでお手伝いさせていただきます。ご希望の土地をお探し致しますのでご相談ください。
- エアコンの一番おすすめのメーカーと機種を教えてください。
-
毎年色んなメーカーの商品を比較しますが、なかなか難しいですね。というのも、エアコンは「何が最高かよりも何が最適か」だからです。家一軒一軒、最適なものが違いますのでここ最近の引き渡しでも機種は殆どバラバラです。
- 小屋裏エアコンから二階の居室へ冷気を送り込むための設備、設計はどのような点を意識していますか?
-
エアコンから出てくる風量をどの部屋にどれだけ配るかという事がポイントです。配る方法は、換気扇を回すか、冷気の自由落下に任せるかのどちらかです。また、どちらにしても、冷気を配るだけではなく、その元になる空気をどこから持ってくるかも大事です。それも、吹き抜けなどを通して供給するか、ダクトを縦に配管して供給するかになります。
後は、配管をする場合は、それなりの風量になりますので、ファンの音の問題が出てきます。最後に、基本的な事になりますが、空気の熱容量と送風量の計算をしっかりせねば失敗します。
- 以前、分電盤から屋外に配線を行うことができるような予備スリーブ穴をあけて引き渡しされるとのことでしたがそれは気密性が高い物でしょうか?私の家も同じ仕様にしたいので、品名品番を教えて頂きたいです。
-
普通のエアコン用のスリーブになります。
型番までは指定しておりませんでしたが、内外が軽くネジになっており、使わない時は気密が保たれている製品になります。
建築会社に言っていただければわかると思います。
- エアコンのグレードについて、高価格帯と低価格帯ではCOPが2~3異なります。生涯コストで考えると、どちらの方が良いのでしょうか?
-
それぞれの設計士さんの思想によるかと思いますが、私の場合は、更新が必要なものに高価なものはなるべく使わず済む様にしたいという思いから、極力グレードの低いエアコンで済む様に各種の設計を行っております。
家の性能がアンバランスであるほど高性能なエアコンが必要になり、家の性能のバランスが良いほど、低機能なエアコンで済む様になります。
COPは定格域では2~3違ってきますが、低負荷域、高負荷域であればそんなに差がつかないものの方が多いです。
高価格帯なエアコンが将来的に元が取れるかというと、ちょっと厳しいかなぁと思っております。
- エアコンによる除湿を突き詰めていくと、顕熱比はどのくらいまで下げられるのでしょうか?
-
安いエアコンでも瞬間風速的に50%程度まではいけます。
ただ、絶えず50%で動いてくれるかというと、そうでもなく、新しいエアコンほど上手にサボろうとしますので、平均では70%とか80%とかになってしまいます。
うまく空調設計をすることで、少しずつ顕熱比を下げることができるようになります。
- G2レベルの性能がある家で二階リビングを採用した場合、一階の床下エアコンによる暖房だけで、二階を十分に暖めることはできるのでしょうか?一階は間仕切りが多くなり難しい場合、うまく活かせる工夫はありますか?
-
出来るかできないかで言えば可能になります。1階であれば、間仕切りが多くとも床ガラリの位置や数で吹き出し量を調整すれば大丈夫です。
ただ、おっしゃることを上手く機能させるためには、きちんとした計算が必要です。
Q値1.6(G2レベル程度)W/㎡K×100㎡(30坪)×20℃(内外温度差)=3200W(家の総暖房負荷)。総二階だとすると、各階1600Wの暖房負荷になります。
例えば1階の足元と2階の室温で空気温度が5℃(K)違う想定でに2階に1600Wの熱を空気に乗せて送りたい場合、1600W÷0.34Wh/㎥K(空気の比熱)÷5K=941㎥/hの空気循環が必要です。(エアコンの最強風量で約800㎥/h)室内にこれだけの空気の流れをどのように作り出すのかという答えを持たないまま設計をしてしまうと、床下エアコンの暖気は2階には届きません。
各部屋、そして全体の温度がきちんと均一になる様に設計がなされているのか、その根拠(計算式など)があるのかが一番大事になります。
イメージや、定性的な言葉だけではきちんとした性能住宅にはなりません。上記のような計算が出来る設計士さんを訪ねて頂ければ大丈夫ですが、出来ない人の場合は大失敗する可能性もあります。
- 6地域でUa値0.4、C値0.5程度で平屋だと何坪くらいまで床下エアコン1台を有効利用できますでしょうか?また、設定温度は何度くらいで運転するのがいいのでしょうか?
-
基礎とエアコンの設計施工が間違っていなければ、平屋で40坪くらいまでは床下エアコンで行けます。40坪くらいにする場合は、やはり床下に大きな圧力を掛けなくてはなりませんので、なるべく大きな風量となるべく高い設定温度にしておいた方が無難です。
- いぐさ畳でも床下エアコン設置は問題ないでしょうか?
-
いぐさ畳でも床下エアコン設置は問題ありません。わずかではありますが、畳が暖かくなりますので、気持ちいいです。
- 床下エアコンを設置する予定で、基礎内断熱で基礎立ち上がりが少なくなるよう地中梁を多くしてグリットポストの立ち上がりにしようと考えています。この場合、根太工法ではなく剛床工法だとうまく暖まりませんでしょうか?
-
基礎の構造はグリッドポストにしておくに越したことはありませんが、空気搬送がうまくいくかどうかは、ちゃんと計算すれば、普通の立ち上がりの基礎でも大丈夫です。
根太工法か剛床かは、どちらでも大丈夫ですが、根太工法は壁体内にも暖気が流れ込んでいく為、空気の抜ける先が多い。剛床は基礎内+床ガラリがメインで暖気を室内に送らないといけない。という違いがあります。違いを分かって計算してくれる方であればどちらでも大丈夫です。
基礎コンクリートから熱が逃げる量は床下エアコンの場合、普通の家の倍くらいありますので、壁の断熱材よりも分厚い断熱が本来は必要です。床面も基礎の上下を問わず全面断熱をしておいたほうが良いのは間違いありませんので、参考にしていただければと思います。
- 床下エアコンを夏に使うと、結露やカビのリスクがあるのは何故ですか?基礎断熱と床にガラリが設置してある家なら、床下も室内と似た環境になると思います。
-
暖気はガラリを通して上に上がりますが、冷気は基礎の下にどんどん溜まり続けるからです。
エアコンから出てくる空気は基本的に湿度100%に近いものです。(露点以下に冷やされ、結露させながら出てくるため)それが床下に溜まり続けてしまい床上から流入した空気をまた結露させるためカビが生えます。
室内も、足元だけが20℃以下、頭の上は30℃みたいな空気になってしまいます。下に溜まった冷気を持ち上げるのは非常に大変です。
- 凰建設さんはどんな施主様にも床下、小屋裏エアコンを提案されてますか?
-
床下エアコン小屋裏エアコン率は6~7割程度です。価値観や生活スタイル、家の性能、間取り、その他諸々勘案して個別に最適な物を提案します。
勿論、風を感じにくい冷暖房程、空間としての質は上がりやすいです。
- 薪ストーブについての質問です。室内の空気を燃焼させるタイプの薪ストーブなのですが、煙突が詰まるとやはり一酸化炭素中毒などのリスクはありますでしょうか?
-
煙突が詰まるような事態が起きるのは、よほどストーブの使い方が悪いと思います。不完全燃焼はCOの発生を起こしたりという可能性もありますので、そうならないようにお使いください。
- 高気密高断熱の住宅という前提で、吹抜けにシーリングファンを設置する場合、その高さは2階天井付近と2階床付近のどちらが効率が良いのでしょうか?
-
高気密高断熱のレベルによります。
レベルが高いほど、天井設置の方がよく、レベルが低いほど、2階床付近設置の方がまだマシという風になります。UA値がG2より良くて、窓が樹脂トリプルレベル、C値が0.3以下であれば天井、それに至らなければ床、くらいでしょうか。勿論外部の気象条件によります。
- 二階の締め切った個室にエアコンの冷気を届けるためにエアパスファンの設置を検討していますが、機種選定や設置方法、使い方で注意点はございますでしょうか?
-
設計者さんが空気線図を理解しているかどうかですね。空気線図の読めない設計者さんが「勘」で送る空気の温度や量を決めた物が成功している例は少ないです。殆どが風量不足。成功しているもののうち、風量が適正な物は僅かで、残りは過大設計になっています。
換気に何を使おうが、家の熱負荷というのはトータルで考えねばなりません。外皮は、内部発熱は、日射取得は、、と計算したうえで、必要量を締め切った個室に送ります。
注意点と言えるかどうかですが、そもそもちゃんと計算している?根拠ある?という所ですね。
温度は物理です。魔法ではありません。計算した通り以上の物は実現しません。
- 脱衣所に壁付き扇風機を施工することはありますか?
-
過去には付けたこともありますが、今は殆ど扇風機を付けることはありません。付ける理由は恐らく夏場に火照った体を冷ますという事になるかと思いますが、一部屋分を冷やすエネルギーで家中が冷えればそういう物が必要なくなります。
- 凰建設で乾太くんを設置する場合、近くに差圧式給気口は設置していますか?
-
差圧式給気口は付ける場合もあればつけない場合もあります。空調計画によるといった感じです。
- 貴社はエコキュートのメーカー、容量、性能等を、お客様の要望、生活スタイルを聞いて、どこにポイントを置いて選定されていますか?
-
まずはAPFです。
また、太陽光を自家消費にするか売電にするかによっても最適なメーカーは変わってきます。また、お風呂に入る時間が夜型なのか朝型なのかによっても、少し考慮すべきことは違ってきます。
- 一体型トイレは、ウォシュレットが壊れた際に便器も交換しなければならなくなるのでやめた方が良いと伺いました。TOTOの一体型を見るとウォシュレット部分だけ交換出来るようですが、このような場合でも一体型は避けた方がいいですか?
-
勿論、交換はできますが、大体10年経つとフルモデルチェンジ、その後約6年経つと部品の取り置き期間が終わります。
この数十年、それで幾度となくメーカーには騙されてきました。
それこそ古い車みたいに、部品取り替え用にもう一台交換用のウォッシュレットを用意しておくような話になったりもしますので、やはりあまりお勧めはできません。
- 食洗機を国産にしようか海外製にしようか迷っています。施主の生活スタイル、予算によると思いますが、森さんのオススメなどありますか?
-
こういう住宅設備を選ぶ際に、基準にしていただきたい物があるのですが、「どこの国がその設備を一番使っているか」です。
例えばエアコンは圧倒的に日本で普及しており、日本のエアコンは世界で最も性能が高いです。薪ストーブは北欧やヨーロッパの普及率が高い為、そちらの製品を選ぶとよいです。熱交換換気はスウェーデンやドイツです。ウォッシュレットは日本ですね。
食洗器についていえば、日本の普及率は3割、ドイツでは8割です。という事は、やはりミーレやボッシュなどの海外製の物の方が良い物が多いという事は間違いなく言えてしまいます。
ただ、食器事情はドイツと日本では若干違い、あちらはお皿文化、日本は器文化です。食洗器自体がそもそもお皿を洗うためのものですので、あなたの食卓が器中心であれば、器を洗いやすくしてある日本の製品の方が良いかもしれません。
そのほかにも生活スタイルなどにより最適解は違ってきます。
- メンテナンスコストを低く抑えるためにキッチン選びで大事なことはありますか?
-
キッチンのメンテナンスは、水栓金具、調理機器、換気扇、食洗器等の、水や電気、ガスや空気が流れる場所が殆どです。これも、ホームセンターや楽天などで買えるものを選ぶとよいです。水栓金具が足元でも止められるような商品を選ぶと、将来的に交換は大変になります。
- 今回、新築において太陽光の自家消費を採用するのですが、将来の蓄電池設置に備えて新築時に仕込んでおいた方が良い工事(先行配管など)はあるのでしょうか?
-
高断熱の家の場合、後で外壁に穴を開けるのはリスクも大きいし大変なので、予備の穴を開けておくのが良いです。
分電盤から天井裏を通って、外壁の外につながるような位置だと、後で工事をした際に露出配線などが少なくて済むかと思います。
- 太陽光発電モニターではなくHEMSを導入するメリットはありますか?
-
HEMSのメリットは「計るだけダイエット」効果です。スマホやモニターでいつもエネルギーの使用状況をできるようになり、それを気にして見るようになりますと、自分の生活において、何が沢山エネルギーを使っているのかが分かります。効率の良いエネルギーの削減ができるようになります。
- 凰建設さんで給湯エネルギーの省エネを目的に太陽熱温水器を導入されることはありますか?
-
太陽熱温水器は非常にお勧めです。しかし、エコキュートとの相性はあまり良くないので、悩ましい所です。 賢いタンクみたいな製品が登場して、太陽熱温水器とヒートポンプを制御してくれるようになると、みんなが上手く同居できるようになり、非常に省エネが進むのですが、、、それはまだまだ先ですね。
- 太陽光発電を検討中です。予算が厳しい場合、リースはおススメできますか?
-
予算が厳しくない場合でも、無料で太陽光の仕組みをお勧めしております。Looopやリクシルテプコ、京セラ関電エナジー他、無料もしくはリースで太陽光を載せる仕組みは沢山ありますが、これらはいい意味でここ数年しか通用しない限定的なビジネスモデルです。つまり今の時期に家を建てる方だけが使えるボーナス的な物ですので、使っておいた方が良いです。自費で太陽光を載せる人が初期コストを回収できる確率はそうそう高くありません。
- 屋根一体型の太陽光発電はやはり代替性がないことから森さんの中では選択肢から外れますか?同商品のメリット・デメリットについてお考えなどございましたら、ご教授いただけると助かります。
-
実は弊社社屋の屋根についている太陽光は、20年前のパネル屋根一体方式の物になります。
仰るようにあまり機能を混ぜるのは好きではないので、積極的にお勧めはしておりませんが、外観はかっこいいなと思いながら見ております。太陽光としての寿命が終わった後、普通の屋根材としてずっと使え、更に上から太陽光を載せる事が出来るのであれば、使ってみてもいいのではと思います。
- 長期的なコストや温熱環境の視点からおススメの床材はありますか?質感として、暖かく感じる材質が良いと思っています。
-
まず質感と温かみについてですが、
硬くて重い床材程、傷付きにくく、足の裏がひやっとします。
柔らかくて軽い床材程、傷つきやすく足の裏は暖かいです。前者はタイルなどが挙げられ、後者は木材です。
木材の中でもナラなどの広葉樹は硬くて重く、
杉やヒノキなどの針葉樹は柔らかくて軽い傾向にあります。また、いくら柔らかくて軽い床材を選んでも、そもそもの
室温や床の表面温度が低ければ、暖かさは感じられません。長期的なコストという点では、まず床材を「一生モノ」と
捉えるかどうかが一つのポイントになってきます。お寺の境内の床などは厚さ4cm以上の無垢材が使われますが、
あのレベルの物になりますと、少なくとも家を建てた世代の人が
死ぬくらいまでは長く持つ床になります。(紫外線や雨が当たらない前提)
建築の内装材については、一般に建物の想定使用期間と同じ耐久性を
持つ素材が、生涯コストで最も安くなる材料と言えます。勿論例外もありますが。
そういった意味では、杉の厚板は、花粉症も温熱も温かみも兼ね備えた床材と言えるかもしれません。
2階の床に関しては、耐震等級を考えるのであればどうしても24mmであったり28mmといった厚みの合板を施工することになりますので、あまり厚い床板を施工することは一般的には致しませんが、1階であれば、杉の厚板を使う施工もありなのではと思います。
今の技術の合板がどうなるかは、まだ分かりませんが、30年ほど前に施工された合板のフロア材などはどうしても合板の接着面が劣化し、人がよく歩く場所で床がたわんでしまうという例が多いです。
当時は12mmの厚みの床を1枚だけという施工も多かったので、
合板というだけの原因ではないかと思いますが、
層が剥離する可能性というのはゼロではありません。ちょっと適切な回答になっているか自信がありませんが、参考にしていただければと思います。
- 漆喰、珪藻土は調湿効果が有ると聞きますが、高性能住宅でもビニールクロスよりは梅雨時期など快適になりますか?
-
珪藻土、漆喰の調湿効果が生かされるのは中間期です。
本当に湿気の多い梅雨~8月や、水分の絶対量が少ない冬は空調(加減湿含む)無くして快適にならないのは内装材を変えても同じです。
湿気の計算をされた高性能住宅は最低限無くては話になりません。それに加えて少し湿度変化がまろやかになるのが珪藻土や漆喰になります。どちらを選ぶかという話でもありません。
- ダウンライトについて、電球交換可能なものにするべきかどうか悩んでおります。森さんはどちらを推奨されていますか?
-
今は電球交換タイプでなくても良いと思います。昔の照明は電球部分とその他の耐久性に大きな差がありましたので、電球交換は必須でしたが、今は電球部分とその他の部分の耐久性に殆ど差が無くなってきましたので、壊れたら器具ごと交換でも良いと思っております。もちろん、心配であれば電球を交換できるタイプの物にされておくのも良いと思います。
- メンテナンスコストを考えますと、屋根、外壁、樋の素材をガルバリウムに合わせるなどすることが生涯コストを押さえることにつながりますか?この場合、漆喰などは耐久性が異なるため混ぜるな危険でしょうか?
-
素材を合わせるのはメンテナンスコストを抑えるためには有効です。
ただ、壁は漆喰、屋根はガルバなど、影響の少ない混ぜ方もありますので、絶対にやってはいけないという事はありません。
屋根材の耐久性の方が上に乗る太陽光パネルよりも短いなどの例が、混ぜるな危険です。
外壁の耐久性よりも、外壁にくっつける設備品の方が長持ちするというのも残念な例になります。
- 木製玄関ドアでおススメはありますか?メンテナンスが大変だと思いますが、やはり雨で濡れにくい設計が大事になってきますか?
-
気にしていただきたいのは雨と陽当たりです。木材は雨と紫外線で変化していきますので極力雨と紫外線を当てない方が良いです。
性能がしっかり出ればどこのメーカーのものでもOKです。
ユダ木工さんやガデリウスなどを使ったことがあります。
北海道にある「ノルド」さんと言う建具メーカー
北陸のキマドさんと言う建具メーカーの玄関ドアは
機会があれば使ってみたいなと思います。ちなみにメンテナンスですが、理想を言えば、最初は細かくメンテナンスを行い、塗膜の厚さや浸透するオイルの量をぐっと増やしておくと、比較的長持ちいたします。車の塗装も傷んでからコーティングをするよりも傷む前にコーティングをかけてしまった方が長持ちするのと同じです。
- 凰建設さんはリクシルのSWを使用されているようですが、SW工法は2×4工法のように外せない壁等により間取りが制限されることはあるのでしょうか?
-
大層な名前なので、特殊な工法に見られがちですが、断熱材と構造用合板が一緒になったLIXIL製の壁パネルを柱間に後から入れるだけという非常に単純なものになります。普通の在来工法の設計と変わることは何一つありませんので、制限が増えるという事は有りません。
- 土地の南面が幹線道路に面しており、防音面で不安です、設計上で注意できる点はありますか?
-
音はざっくりと低い音と高い音に分けて考える必要があります。高い音とは、タイヤの走行音の「シャー」と言う感じの音になります。低い音とは、大型車のエンジン音や走行による振動を伴った音になります。
高い音を防ぐために最も大事なのは、密閉性です。音楽を聞くときにイヤホンだと高いシャカシャカ音が漏れますが、耳を覆うヘッドホンタイプですと、高い音はほぼ漏れません。窓を機密性の高いものにする、換気の吸気口をその面に持ってこない、持って来る場合は外壁通気層からの導入にするなどの対策が有効です。
低い音を防ぐのは躯体の振動を止めることが大事です。地面が車の振動に合わせて揺れてはどうしようもありませんので、地面の振動を止める目的も併せて地盤改良を行なったり、支持杭を打ち込んだりします。木構造の硬さを上げる目的も併せて耐震の等級を上げたり、揺れにくいようにしていきたいです。また、外壁の素材を重く、厚いものに変えたり断熱材を比重の大きな材料にするのも有効です。
まとめますと、家を丈夫でどっしりと作っていくこと、隙間をできる限り塞ぐことに気をつけていくと良いと思います。
また、事後の対策として、ノイズキャンセル機能のあるスピーカーを設置するということもできます。今はまだ種類も少なく高価ですが、どんどん金額は下がっていくのではないでしょうか。
最後に、逆転の発想で、室内を絶えずうるさい状態にしておくという対策もあります。一定以上の音が絶えず出ている状態であれば、音にだんだん耐性がついていくため、相対的に音が気にならなくなります。
- パッシブハウス基準で家を建てると、冬場でもオーバーヒートになったり寝苦しくなったりするのでしょうか?また、オーバーヒート対策は何かされていますか?
-
オーバーヒートは狙ってさせることが出来るようになります。暑くなり過ぎたら窓を開けて「ああ、涼しい」で大丈夫です。夜寝苦しいレベルになることは余程ありません。オーバーヒートをするという事は窓が大きいという事で、夜に逃げる熱も大きくなっていきます。
私の場合、オーバーヒートをさせるかどうかは住まい手さんの生活スタイルによります。夫婦共働きで日中は殆ど家に居ませんという家庭であれば、存分にオーバーヒートさせておき、夜の暖かさを確保します。
- 省令準耐火構造は施主に説明されていますか?火災保険が半額になりますが建築費用が余分にかかるのでコスパがどうなのか伺いたいです。
-
最初のアンケートで「省令準耐火にしたいか」を聞きます。
何それ?という方には説明をして、YES/NOで答えられる方はそのようにします。
省令準耐火は、正しい省令準耐火と、偽省令準耐火がありますが、火災保険の割引はどちらも同じです。そして、正しい省令準耐火は循環ファンや配線胴縁ができません。また、偽省令準耐火は保険会社に対する詐欺になるかどうか、かなりグレーな事になります。
そういった事を説明したうえで、省令準耐火にするかどうかを決めるようにしております。
- 0歳の乳児に適した温湿度はあるのでしょうか?夏休みということで親族が集まるのですが、赤ちゃんから祖父母まで好みの温湿度が違うような気がしております。
-
例えば病院の温度は24℃を基準に、冬はー2℃、夏は+2℃程度に抑えられるように空調設計を致します。
抵抗力の弱い赤ちゃんやお年寄りの方にはそのくらいの環境を用意してあげられると良いですね。よほど家の性能が良く、それにマッチした空調が無い限りは、日本の夏で除湿のし過ぎという事は起こりません。安心して冷房と除湿をつけてあげてください。
- 地鎮祭や上棟式では何をするのですか?
-
家を建てる工程で記憶に残る行事のひとつです。地鎮祭は 神社やお寺に依頼して、その土地をお祓い清め、工事の安全と 家内息災を祈願するものです。上棟式にも同様の意味があり、家を建てる工程で記憶に残る行事のひとつです。最近は見かけなくなりましたが「餅まき」もこの日に行います。
- 上棟のご祝儀にいくら包めば良いのか迷っております。予算が余ってる訳ではありませんが、長いお付き合いになるのでお渡ししたいと考えております。棟梁制の会社でご担当者ががっかりしない額を伺いたいです。
-
これは地域によっても相場が違ったりしますので、素直に現場監督さんや設計士さんに相談してみてはいかがでしょうか。
棟梁にまとめて渡す方法もありますし、上棟の際に参加していただいた方全員に渡す方法もあります。お金ではなく、お酒などにされる方もおられます。
金額も5,000円~3万円程度と、バラバラです。
少なかったからと言って残念に思う人はいないかと思いますので。あまり気にしなくても良いかと思います。
- 家の引き渡しの後、大工さんへの謝礼やお世話になった工務店さんへのお中元やお歳暮は送るべきでしょうか?
-
施主様からお中元やお歳暮を貰うことはもう殆どありません。
完成時は金額や品物云々ではなく、お子さんが描いた家や大工さんの絵とかそういうものも非常に嬉しいです。
- 上棟に1日立ち会いたいと思っています。休憩の飲み物やお昼のお弁当は用意した方が良いものでしょうか?
-
どちらでも構いません。差し入れがないからと言って残念には思いませんし、作業の手を抜くという事もありません。もちろんご用意いただいた際には有難くいただいております。気軽な気持ちでご自身の家づくりを楽しんでいただけたらと思います。
- 地鎮祭の神主さんは自分で手配するのですか?
-
元々お付き合いのある神社がおありでしたり、建設地のものすごく近所に神社があるという場合はそこに依頼することもございます。ない場合には弊社で手配しております。道具の名前などあまり聞きなじみがないと思いますので、お客様手配の場合にも持ち物の確認などは間に入って行わせていただくことが多いです。
- 気密測定を普段しない工務店は、ドアを閉めた状態で薪ストーブの火がつきにくい、シンクの水が流れにくい、ドアが開いたらスムーズに水が流れるから気密測定しなくても高気密住宅と言いますが合っていますか?
-
絶対にダメだとは言いませんが、私の周りにはそういう工務店はおりません。模試を一回も受けたことは無いけどもクラスの中では頭が良い方だから東大合格間違いなしと言っている受験生をどこまで信用するかみたいなものでしょうか。
- 気密測定の時期、回数、その際に気をつける点について、どのようにお考えでしょうか?
-
理想を言えば気密施工完了時と入居前の2回行いたいです。
弊社は2回やっておりますが、気密施工には大体1回あたり5万円~10万円のお金がかかりますので、住まい手さんがそれを良しとするかも大きなポイントです。
よくやりがちだけど絶対やってはいけないのが、窓の目張りです。特に引き違いを目張りすると極端に上振れした値が出ます。
0.5を下回ってくると、漏気はほぼ窓からになります。0.5までは施工、0.5からは窓の選定が気密を下げるポイントになります。
- 中間気密測定で、C値0.46だったのですが玄関扉を目張りして測ったところ、C値0.39になりました。玄関扉が弱点になっていると考えて良いでしょうか?
-
おっしゃる通り、玄関ドアは漏気箇所になりやすいところではありますがC値0.5なら十分高性能ですので、そんなに気にしなくても大丈夫ですよ。
- 気密測定時に窓の縁などにテープを貼っていたりする様子を見たことがあるのですが、そういった方法が一般的なのでしょうか?
-
気密測定時には、測定機器がつく窓以外は目張りをしてはいけません。
- 気密測定は、中間時に比べて完成時はどれくらい悪くなることが多いてすか?
-
中間時も完成時も大きく変わりません。
- 建物は何日で完成するのですか?
-
家の大きさによりますが建てはじめると、約5~6ヵ月で完成します。しかし、事前のプランニングは別です。住み心地良い家つくりにはプランニングが重要になります。専門スタッフと一緒に、納得がいくまでプランニングを行います。
- 工事中、大工さんにお茶出しなど必要ありますか?
-
お気遣いなさらずご見学くださいませ。現場監督を始め大工さんや職人さんが誠心誠意、一棟、一棟造らせていただきますので、どうぞ御気兼ねなく、何度でも現場に足を運んでいただきお声を掛けて頂けるだけで励みになります。
- UA値0.3、C値0.3、床断熱で玄関土間の立ち上がり断熱材を入れたほうが良いでしょうか?
-
どれだけ薄くても良いので入れてもらうべきです。その性能でコンクリートの熱橋がありますと、質問者さんの住み方次第では土間立上りで結露が発生し続ける可能性があります。気が付いたら立上り面にカビが生えているという事態を招く恐れがあります。
日本の住宅性能の計算基準ではそういう部分の熱橋はほぼ無視して計算されますが、UA値が0.3程度になってきますと、各種熱橋部分からの熱流入が無視できなくなってきます。熱橋まで含めて正確ににUA値計算をすると、0.03~0.1程悪くなってしまうという事もありますので、そのレベルであれば、きちんと熱橋処理をしてもらった方が諸々良いかと思います。
- 凰建設では、基礎の養生期間はどのくらい取っていますか?最近建った近所の建売は3日ほどでしたが、季節等によってちょうどいい長さはあるのでしょうか。
-
早く固まるコンクリートを使うと、早く型枠を外したり土台を乗せたりすることができるようになりますが、土台を伏せてアンカーボルトを締めるまでであれば、3日は早すぎる気がします。
弊社は大体立ち上がりの打設から上棟まで2週間程度見ております。
季節はあまり関係なくそのくらい、養生を取ります。
- 現在、セルロースファイバー施工中ですが屋根断熱の厚みが当初200mmの契約だったのですが150mmしか厚みが取れず吹き込めなかったと言われてしまいました。そこで、セルロースファイバーの内側にネオマフォームを付加するか、天井にネオマフォームを付加する提案をされてますが、このような施工は問題ないのでしょうか?この方法以外にリカバリー方法はありますか?
-
ネオマフォームを屋根断熱の下に付加するやり方で問題ないと思います。断熱材は組み合わせて使っても大丈夫です。屋根断熱と天井断熱は、端部の気密がしっかりとれていれば併用しても良いかと思いますが、出来ればどちらかにまとめたほうが、効率は良いと思います。
- 子供が嘔吐したり、ホットプレートで油がかなり飛んだ場合等は、無垢床や無垢テーブルはアルコールで拭いても大丈夫でしょうか?また、無垢材を保護するには、どのような点に注意して生活すればいいでしょうか?
-
アルコールや他のアルカリ性のもので拭いたりすると無垢は黒く変色しますが、色が変わるだけで、質が悪くなるわけではありません。
色が変わるのが嫌だということであれば、無垢を無塗装で使うことはあまりおすすめ致しません。
また、汚れや傷が付くのを避けたい場合、無垢材の上に、何かしらの養生やコーティングをしてしまう。定期的に養生やコーティングを更新するというのが答えになります。この場合の養生とは、市販のキッチン用マットでもいいですし、無垢材を覆ってしまうくらいのクッションフロア(接着はしない)などの措置となります。
- 床を無垢のヒバフローリングにしました。仕上げに蜜蝋や自然塗料を塗った方がよいですか?無塗装の方がよいですか?
-
ヒバの無塗装の匂いが私は好きですが、水のしみこみなどが気になるようであれば、蜜蝋などを塗ってあげてください。
私は無塗装でもいいと思います。
- 木製の玄関ドアに傷がついているのを見かけました。木製の玄関ドアは補修や交換は出来るのでしょうか?
-
ガデリウスの表面の傷は丁寧にペーパーを掛けて再塗装すれば分からなくなると思います。玄関ドアや窓は交換ができる前提で商品が作られておりますので、交換は勿論可能です。
傷を我慢できるかどうかという物差しは、住まい手さんの物ですので、どうしても我慢できなければ交換という事になるかとは思います。
無垢の材料ですので、どうしても傷は付きやすいです。将来的に生活の中でもちょこちょこ傷は付いていきますので、できればおおらかな気持ちで使ってあげてもらえればと思います。
- ウッドデッキの塗装は何年くらいで塗り替えるのが良いのでしょうか?DIYでも耐久性に問題はないですか?
-
ウッドデッキの塗り替えは5~10年に1度やられると良いです。見た目の塗装の剥げも気になるかと思いますが、塗料には防腐効果もありますので、木材の耐久性にも効果的です。DIYでも支障は出ませんので、是非日曜大工で頑張ってみてくださいませ。
- 漆喰の壁に落書きをされてしまいました。何を使って汚れを落とすのが良いでしょうか?
-
メラミンスポンジやサンドペーパーで表面を削ることで汚れを落とすことができます。もし下地が見えてきてしまった場合は指で良いので上から漆喰を馴染ませてあげれば問題ありません。
- アルミ樹脂複合サッシを採用して冬の寒い日に表面結露が発生した場合、壁の内部や躯体にも悪影響を及ぼしていると考えた方がいいでしょうか?
-
ガラス表面にできる結露は雫になって垂れなければ躯体に悪影響を及ぼすことはありません。
枠部分に結露が出来ている場合は、目に見えない躯体側で結露している可能性はゼロとは言えません。施工の方法などによりケースバイケースです。生活の中において、躯体ダメージのリスクなく実現できる温湿度を設計士さんにきちんと計算してもらうことをお勧めします。
- どういった仕組みで窓の外側が結露する現象は起こるのでしょうか?
-
夜間放射冷却により、窓の表面温度が外気の露点温度に達することで起こります。普通に霜が付いたりするのと同じような現象です。家の中から窓の外に熱が逃げている家(ガラスの断熱性が低い)ですと、窓の外部表面温度が下がりませんので窓の外の結露が起きません。
- ガルバリウム、トリプルガラスの窓を利用している場合、携帯電話の電波が悪くなると思うのですが、どのような対処方法がありますでしょうか?森さんはどのように対処されてますでしょうか?
-
外壁を金属の物質で覆うほどに携帯電話の電波が通りにくくなる問題はよく聞きますね。
最も簡単な解決策は、屋内のWi-Fiをしっかり整備する事だと思います。近年既に電話を掛けるというシーンは少なくなり、携帯電話と言えどもWi-Fiにしっかり繋がってさえいれば不便を感じるシーンは殆ど無いかと思います。どうしても携帯電話の電波を強力にしたいという事であれば、仰るように小型の基地局を家庭内に設置するというのが王道の解決方法になるかと思います。
- 引違い窓にハニカムシェードをDIYで取りつけました。ハニカムシェードと引き違い窓までの離隔距離はなるべく空間をとった方がいいでしょうか?取付位置の目安はあるのでしょうか?
-
厳密にいうと、外の窓、ハニカムとの中間空気層、ハニカムブラインドが一連で断熱として効きます。
そのため、外壁の断熱の中心と窓やハニカムの中心がなるべく一致するほうが熱橋は起こりにくいのですが、おっしゃるように出窓的に使おうと思うと窓に近いところでハニカムを設置したほうが、色々置いたりでき生活は便利になるかと思います。
また、断熱材の中心にハニカムと窓の中心を合わせるという考え方からすると、窓は付加断熱の外側に取り付けるよりももう少し内側に取り付けたほうが熱橋は少なくなりますね。
- 日射遮蔽をするのに後付けできる商品はありますでしょうか?特に、西側の窓が小さいですがありますので日射遮蔽をしたいです。
-
リクシルのスタイルシェードやYKKのアウターシェードは後付けできますしコスパも高いです。より、取り付けコストを抑えるという点では、フック+すだれが最も良いです。
日射遮蔽部材を布や植物にすると、一生モノという訳には行きませんので、定期的な交換はどうしても発生すると思ってください。西側の窓は小さければそのまま直射日光を入れてしまってもさほど問題が無い事もありますので、縦50cm横50cm程度の窓でしたら遮蔽部材を付けないという選択肢も有りです。
- 第三種換気を採用している新築に住んでおります。強風になると決まってトイレやキッチンの換気扇の中からボウボウパタパタと異音がします。第三種換気を使用の場合、これは不具合ではなく仕様によるものでしょうか?また対策はありますか?
-
よくある話です。
特に季節風が強い地域、決まった方向から吹いてくる地域には起こりやすいです。周りに建物が立っている中心市街地や、地形的に山が近くにあったり山の上に建っている家はよく起こります。
外のフードを風の方向に対して効果のある形のものにするなどの対策があります。
どの程度の風が吹く地域なのかにもよりますので、やはり付き合いのある建築会社さんにしっかり見てもらった方が良いかと思います。
- 換気量の調整のために二酸化炭素の測定器を購入しようと考えていますが、手ごろな値段でおすすめの商品はありませんでしょうか?
-
以前は10,000円くらいの物が多かったのですが、コロナ後は4,000円前後の物も発売されているようです。
家庭で使用するものであればそれで十分かと思いますので、安くても良いのでご購入いただき寝室などにおいて、朝チェックする癖をつけておくと良いかと思います。
- 3種換気の高断熱住宅でお風呂のカビを抑制するための方法はありますでしょうか?換気扇を使用する時間やサーキュレーターを併用する方法などあれば、教えて下さい。
-
適切に冷房暖房をして、換気扇を回しっぱなしにしておけば大丈夫です。お風呂だけが暑いとか寒いという状況を作るとカビが生えやすいです。気をつけてください。
- ガルバリウム鋼板の家を建て2年が経過しました。全体的には綺麗なのですがレンジフードの出口部分が汚れてきました。洗剤で洗い流そうかと思っていますが、他にやっておいた方が良い事はありますでしょうか?
-
油汚れであれば弱い洗剤で、普通に雨垂れや埃などの汚れであれば水だけで洗ってあげてください。基本的には塩害さえなければ汚れは放っておいても大丈夫な外壁です。
- コロナやインフルエンザの感染防止のため密を避けることが推奨されますが、高気密による換気と窓を開ける換気ではどちらの方が有効でしょうか?
-
空気が入れ替わればどちらも同じです。家中の窓を絶えず5mm程度開けておくだけで、計画換気と同等以上の換気が出来ますのでそれでもかまわないかと思います。ただ、その場合は防犯性など、換気以外のデメリットもありますね。いずれにしてもしっかり換気をすることは大事だと思います。
- エアコンの中がカビていることが多くあります。床下エアコンを暖房のみで使用していればカビの心配はほぼないでしょうか?あるいは、冷房用のエアコンでも高断熱高気密ならカビは防げますか?
-
日本の本州の場合、エアコンは冷房で使用すると100%カビが生えると思ってください。除湿をするために必ずエアコンの室内機の中で結露を起させるからです。
暖房で使うだけのエアコンであれば、理論上結露が発生することはありませんので、床下エアコンを暖房専用で使うのであればカビの心配はありません。
高気密高断熱住宅の場合、エアコンはシーズン中に回しっぱなしという使い方をされる方も多いと思いますが、エアコンの中の結露水が絶えず冷やされ続け、流れ続け、そして運転による風が吹き続けているのであれば、カビが生える可能性は低下します。しかし、これも100%結露を防ぐことが出来るかと言えば全くそうではありませんので、気休めくらいに思ってくださいませ。
健康のためには、冷房で使うエアコンはシーズンが終わったら専門業者さんにクリーニングをお願いするのが良いです。
- 新築に1週間くらい前(7月)から住みはじめたのですが湿度が70%以上あります。工務店には新築だから木材の水分でそうなると言われたのですが、そのようなものでしょうか?
-
除湿しなければこの季節はそうなります。うまく換気と除湿を回してみてくださいませ。除湿しても下がらなければ設計士さんに相談をお願いします。
- サーキュレーターを購入しようと思うのですが、どんな事に注意してどのような機種を選べば良いでしょうか?
-
まずは何と言っても風量です。
やりたい事に合う風量の物を選ぶことが大事になります。
その風量は断熱性能や設備の性能、間取りによって変わりますので、設計者さんに相談してくださいませ。
- 最近、家を建てたのですが床下エアコンの電気代がかなり高いです。6地域、Ua値0.46、基礎断熱にネオマフォーム30mm、屋根断熱に吹きつけウレタン200mm、壁に吹きつけウレタン105mmです。基礎断熱を補強したいのですが、おすすめの方法はありますか?
-
床下エアコンに基礎断熱30mmでは弱いです。床下エアコンを採用するのであれば、基礎の断熱こそ、壁よりも分厚くしておかねば、大量の熱が逃げてしまいます。基礎の断熱補強は根気次第で自分でもできますので、床下に潜ってたくさん断熱補強をしてあげたり、シロアリに気をつけながら基礎の立ち上がりの外側を保温してあげてください。目安は壁よりも分厚くすることです。
- 暖房と冷房を両方つけると除湿できるとおっしゃっていましたが、エアコンの除湿ボタンはあまり効果がないのですか?
-
梅雨時などに起きる「温度は上げたい、湿度は下げたい」という状況に対しては、「除湿」の運転は意味の無いエアコンが殆どです。(一部高級機種で再熱除湿エアコンがあります。それであれば意味はあります)
- オススメの湿度計がありましたら教えて頂きたいです。
-
予算が許せばnetatmoです。信頼性で言えば「おんどとり」です。見て分かりやすいのは、熱中症指数表示や絶対湿度表記の出来る「みはりん坊」かと思います。
- 私の家は築8年を迎え、もうすぐ10年点検の時期になるため担当営業にどの程度の金額がかりそうか確認しました。すると、「多くの方は10年点検されても特に修繕されません。痛んでるのが分かったら修繕します」と言われましたが本当でしょうか?痛んでから修繕では遅くないですか?
-
恐らく「痛んでいるのが分かってから」の意図は、構造躯体に被害が出てからという意味ではなく、このままいくと構造躯体に被害が出始めそうな外装材などの痛みを確認してから、という意図かと推測します。
メンテナンスには大きく分けて予防保全と、事後保全があります。
まだ使えるけど壊れたときに大変な思いをするから事前にメンテしておきましょうというのが予防保全、壊れてから変えればいいやと言うのが事後保全です。
家庭においては電球などの設備品は、多くの例で事後保全。外装の塗り替えや防水、防蟻の処理は予防保全がなされます。防水や外装については、晒されている状況によりメンテの頻度も金額も大きく違う為、一概には言えませんが、長期優良住宅であれば維持管理の履歴も残りますので、少し早め早めのメンテを心掛けて頂けると良いかと思います。営業さんにその旨を伝え、早めのメンテを依頼すれば良いかと思います。
- 凰建設さんで家を建てたら、住宅設備を選ぶ際のおススメの物やアドバイスはしていただけるのでしょうか?
-
勿論、ご希望いただければ、アドバイスをさせて頂きます。
また、除湿器加湿器については、能力計算をせずに選んで全く意味が無い物が設置されているという事も少なくないので、購入前に必ず相談いただきたいと思います。
- 冬は快適なのですが断熱効果を夏はあまり体感できません。断熱は暑さには効果がないのでしょうか?
-
断熱等級5以上になると夏の暑さの原因というのは断熱よりも日射遮蔽と換気によるところが相対的に大きくなりますので、等級6を超えて断熱を厚くすると効果を感じにくくなるかと思います。
高断熱にしたけど夏が快適じゃないという場合、日射と換気空調の設計を失敗している事を疑ってみると良いかと思います。
- 一年前に新築(C値0.3、UA値0.4)を建てた際に太陽光発電を付けました。当初は卒FIT後に、V2Hを導入するつもりでしたが電気代高騰を受け蓄電池を検討しています。しかし空配管等を設置しておらず、後から壁に穴をあけて蓄電池を設置する場合の注意点を伺いたいです。
-
できるだけ今空いている穴を使うことをお勧めしますので、多少露出配線になってしまうかもしれませんが、エアコンのスリーブなどを使って線を出されることをお勧めします。
それも難しいということであれば、壁に開けた穴のすぐ上に屋根が来ている位置に穴を開けるのが、最も漏水のリスクが少なくなるかと思います。ちなみに、太陽光をすでに付けているのであれば、まずは日中に電気を使う生活に切り替える方が優先です。その上でどうしても蓄電池が必要そうであれば、導入してください。エコキュートと空調を昼間に動かすようにするだけでもかなりの省エネになるはずですので。
- 床下断熱で建てられた家を、リフォームによって基礎断熱にすることは可能ですか。
-
可能です。実績もございます。しかし、基礎の形状によっては大変大掛かりな工事になる場合もあります。暮らしのご希望と建物の状況によって最適なリフォームをご提案します。
- 電気温水器からエコキュートに買い替えを検討中です。エコキュートに変える際、基礎に穴を開ける工事が必要になってくると思いますが、基礎に開けても問題ないでしょうか?
-
構造的にはもちろん穴はない方が良いのですが、そこはやむなしかなと思います。あまり派手に鉄筋が切られない事を祈りつつ、穴を開けてもらえればと思います。
また、基礎ではなく土台より上であけることができるかもしれませんので、一度検討してみてもらっても良いかもしれません。
- 和室の畳をフローリングに替える事を検討しているのですが、凰建設ではリフォームもやっていますか?
-
はい、そのようなリフォームも承っております。
- リフォームの依頼はどのようにしたらいいですか?
-
まずは電話またはHPの無料住宅相談からお問合せくださいませ。リフォームや増改築は実際に現地を拝見させていただいてから御見積を提出させていただきますので、ご都合の良い日時にお伺いさせていただきます。
- 建売のような性能が比較的低いであろう物件であっても、築20年以内で劣化が少なければ新築よりもコスパ良く高性能な物件が可能なのでしょうか?耐震なども考えると、逆に新築よりもあるいは新築並みに費用がかかるので新築の方が費用的にも良いということにはならないでしょうか?
-
耐震等級3を目指すと、かなり大掛かりな施工になりますので、難しいかなと思いますが、現行の耐震等級1かつ断熱をG2グレード程度にという事でしたら、築浅の物件をリノベした方がコスパ良くできる可能性が高いです。勿論、インスペクションをして、構造自体の劣化が無いか、補強不可能なダメージが無いかを調べてみるのは必須です。
デメリットとしては、やはり設備や間取りが新築の様に自由にならないという事ですね。
- 打ち合わせに子供を連れて行っても大丈夫ですか?
-
キッズコーナーもご用意しておりますので、ぜひご家族でお越しください。
これまでにいただいた質問
- 予算の中に工務店さんへお支払する設計費用・構造計算費用・長期優良住宅申請費用・確認申請費用・完了検査申請費用・設計監理費用があると思いますがいくらぐらい見込んでおく必要があるのでしょうか?
-
設計事務所さんですと、工事費の1割程度が目安になります。
工務店だとその半分くらいかなと思いますが、工務店の場合は工事費の利益の中に設計費用を分散して入れ込んでしまい、設計費用という項目を殆ど計上しないということもできますので、実態はバラバラだと思います。
現実的に会社の原価から計算すると、依頼する工務店の設計士さんと会った時間×2万円+各種申請の実費くらいは会っていない時の作業も含めて掛かっておりますので、私は掛かっている費用を素直に見積もりに計上した方が、後々辻褄の合わないことが起こりにくくて良いのではと思っております。
- 坪単価って何ですか?
-
坪単価とは、家を建てるときの1坪当たりの建築費のことです。建物の本体価格を延べ床面積(坪)で割った数値のことです。1坪はおよそ3.3m²で、家を建てる時のおおよその目安として一般的に参考にされています。例えば延床面積30坪の家が2400万円だとしたら、坪単価は80万円ということになります。
- 自己資金はどれくらい必要ですか?
-
設計申込の際に50万円(税抜)をお預かりします。住宅ローンを組むには自己資金が1割程度は必要だと言われますが、資金についてのご相談も無料住宅相談で承っております。
お申し込みはこちら→https://www.ohtori.net/reserve/
- 候補の土地から50mのところに電話会社の鉄塔があります。ネットで電磁波で健康被害が出ると記事がありましたが、どのようにお考えですか?また、電磁波を防ぐ方法はありますか?
-
GHz帯の電波の場合、電波防護指針の基準値は61.4V/mという電界強度以下が求められます。デジタル携帯電話基地局のアンテナ基地局から発せられる対象とする空間における電界強度は50m地点であれば0.5V/m前後であることが多いと言われています。
それでも気になるようであれば、電磁波をはじく目的で、基地局アンテナ方向の屋根や壁面にアルミを蒸着させた遮熱シートなどを施工すると良いかと思います。窓はブルーやブロンズのLow-Eガラスにした方が良いかと思います。
ちなみに、一般的なノートパソコンから発せられるゼロ距離の電界強度は1500V/m前後になります。
電磁波が気になるようであれば、家の外からやってくる電磁波よりも、家の中で発生する電磁波の対策が優先かと思います。
- 伊勢湾台風以来1度も水害が無い、伊勢湾や長良川に近い1種低層エリアでは新築しない方が良いですか?
-
長島-桑名-四日市あたりの場合、台風もですが、地震による地盤の崩れや津波の方が心配かなと想像致しました。
ハザードマップをよく確認していただければと思います。