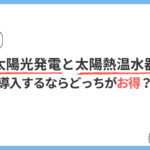HOME BUILDING TIPS お役立ちコラム

【住宅の生涯コストを考える】家づくりの資金計画は超重要!
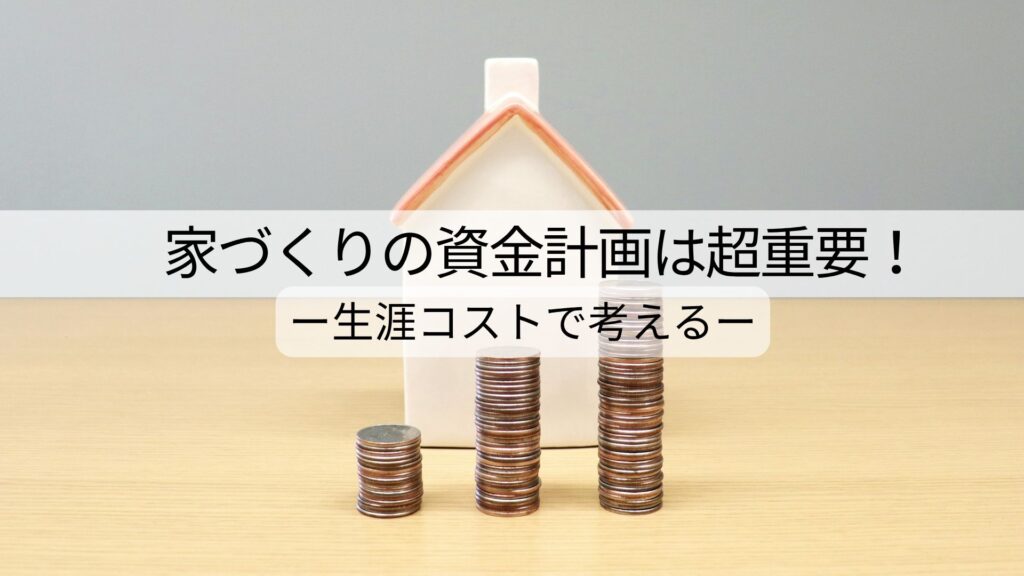
こんにちは、凰建設代表取締役の森です。
「家づくりはいくらかかりますか?」
よく聞かれる質問ですが、実はここに大きな落とし穴があります。
多くの方が気にするのは建築費。しかし家づくりにはその他にも多くのお金がかかります。特に、建てた後の修繕費、光熱費、税金…これらの「生涯コスト」が、実は家計を最も圧迫します。
夢のマイホームを考えるのは、とても楽しい時間ですよね。そのワクワクをずっと続けるために、安心できる暮らしの計画を立ててみませんか?
知っているかどうかで、30年後の家計が大きく変わります。ぜひ最後までご覧ください。
家づくりにかかるお金の全体像
家づくりの資金計画を正しく立てるには「家を建てる」以外のお金まで最初に把握しておくことが肝心です。ここでは主な出費の種類を紹介します。
家づくりに関わる3種類の出費
家を建てると、将来を含めて以下の費用がかかってきます。
- 初期費用(本体、付帯工事、申請・登記、外構、照明・カーテン、家具家電、引越しや仮住まいなどにかかる費用)
- ランニング費用(光熱費、固定資産税、火災・地震保険、通信費など)
- メンテナンス費用(設備の更新費、外壁・屋根・内装の修繕費、点検費用など)
「家を建てる」お金は初期費用の一部にすぎず、実際にはより多くの費用が発生するのです。
「借りられる額」と「返せる額」は違う
住宅ローン審査上の「借入可能額」は上限目安であって、家計に無理のない「返済可能額」とは一致しません。返済負担率は毎月手取りの20%以下を目安に、ボーナス払いなしで設計するのが安全策です。
坪単価だけでは総額は読めない
また、住宅広告などでは坪単価が表示されることが多いものですが、坪単価は本体価格の指標に過ぎません。
一般的に、地盤改良、屋外給排水、外構、申請・登記費用などは別計上になります。広告の坪単価だけで「家づくりにかかるお金」を判断するのは危険です。
上記を理解した上で、資金計画を立てていく必要があります。
資金計画の重要性と注意点

資金計画の甘さは家づくりの大きなリスクとなります。後から後悔しないよう、以下の点に注意してください。
あとから費用が膨らまない家づくりを
多くの建築会社は契約を取りやすくするため、初期の資金計画を低めに提示する傾向があります。
契約後に住まい手が後戻りできない状況になると、付帯工事や諸経費、仕様変更などを理由に金額を追加し、最終的に当初の予算を大きく超えてしまうケースが少なくありません。
こうした事態を避けるには「最初の見積りにどこまで含まれているのか」を見極めることが不可欠です。この乖離が起きやすい構造を理解しておくと、安心して家づくりを進められます。
すべてを含めた資金計画を立てる
資金計画を立てる際に大切なのは、建物本体の価格にとどまらず、実際に暮らしを始めてから必要になるあらゆる費用を見落とさないことです。
付帯工事や申請関係の諸経費はもちろん、カーテン・照明・家具・家電、引っ越しや仮住まいにかかるお金も現実的には避けて通れません。
さらに、毎月の光熱費や固定資産税、将来の修繕・設備更新といったランニングコストまで想定しておくことが大切です。
ただ、家づくりは誰しも初めての経験で、多くの方が人生一回きりのもの。かかるお金の全体像を把握するといっても、住まい手がここまで一人で考えるのは非常に難しいことです。
資金計画というのは、多くの建築会社が実施してくれるものですが、その精度と内容は会社によって様々です。上記のリスクを知ったうえで受ければ、どんな資金計画書を提示してくれるのかによってその建築会社の誠実度が図れるはずです。
結果として初期の金額は大きく見えるかもしれませんが、これこそが「後から困らない」ための唯一の方法です。最初から全体像を把握しておくことで、家づくりは安心と納得を持って進められます。
将来の不動産管理コストを織り込む
家を建てる前に、将来自分が管理することになる不動産について考えておくことも欠かせません。
例えば実家を相続する予定があれば、その建物や土地を維持するために固定資産税や管理費が必ず発生します。
もし新築を建てたうえで相続不動産も抱えることになれば、二重の負担が家計を圧迫し、長期的には大きなリスクとなりかねません。
土地を新たに購入するのではなく、実家をリノベーションして住み継ぐことも、生涯コストを抑える有効な手段です。
家づくりの資金計画を立てる際には「これからどの不動産を所有することになるのか」を整理しておくことも欠かせないのです。
収入に合う住宅ローンを計画する
住宅ローンを計画する際に最も大切なのは、毎月の安定した収入で無理なく返済できることです。
ボーナス払いに頼る計画は、収入が変動したときに一気に破綻のリスクを高めます。返済計画を立てる際には「今の会社を離れても同じ水準の収入を得られるか」を冷静に見極めることが必要です。
自分の稼ぐ力を客観的に把握し、その範囲でローンを組むことが安全な家づくりにつながります。
生涯コストを抑えるための家づくり

初期費用だけに目を向けず、将来の修繕や設備の入れ替えまで見据えて考えることが、資金計画に失敗しないコツです。以下で、生涯コストを抑えるためのポイントを紹介します。
交換頻度の高い仕様を避ける
国の「住宅市場動向調査報告書」によると、リフォームで大きな費用がかかる項目のトップ3は「外まわりの改善・変更」「住宅内の設備の改善・変更」「冷暖房設備の変更」とされています。
具体的には、外壁や屋根の塗り替え、キッチンや浴室・トイレの入れ替え、エアコンなど空調設備の交換です。
これらは一度だけでなく、10年〜20年ごとに繰り返し発生するため、交換頻度の高い仕様を選ぶと生涯コストが膨らみます。
したがって、家を建てる段階で「どの部分がどれくらい持つのか」を理解し、メンテナンスの手間や周期をできるだけ減らせる選択をすることが、長期的に見て最も賢い投資になります。
高耐久な素材を選ぶ
生涯コストを抑えるには、建築段階でできるだけ耐久性の高い素材を選ぶことが重要です。
例えば、外壁では、岐阜の気候でいうとガルバリウム鋼板が圧倒的な耐久性を誇ります。実際に弊社の施工実績では30年間ノーメンテナンスで使用できている例があります。
屋根についても、同じくガルバリウム鋼板や瓦のように長寿命で劣化しにくい素材を選ぶことが安心につながります。
一方で、塗り壁や板張りは外観のアクセントにもなり人気がありますが、定期的な塗り替えが必要になることがあります。選んでいけないことはないですが、メンテナンス費用をコツコツ準備しておかないと、急な多額の出費に苦しむことも予想されます。
つまり、素材選びの段階で「どれくらいの頻度でいくらぐらいのメンテナンス費用が必要になるのか」を考えておくことが、将来の出費を大きく左右するのです。
メンテナンスイージーを目指す
メンテナンスは住まい手にとって楽しくない出費です。
そのため、新築時の初期投資を多少増やしてでも、メンテナンスの必要の少ない耐久性の高い材料や工法を選択することが賢明です。
例えば、耐久性を高めるためには以下のような工夫が考えられます。
- 外壁材や屋根にガルバリウム鋼板や瓦を採用する
- 雨漏りや結露による劣化のリスクを減らせるよう、家はシンプルな形状に設計する
- 雨から外壁や窓を守れるように軒を設ける
住宅を100年持たせるようにしっかりと家を作っている場合には、100年ノーメンテナンスというわけにはもちろんいきません。愛情を持って家をお手入れをすることは家を長持ちさせる秘訣です。
塗装や部品の交換など、足場を建てなくても手の届く範囲であれば、高額な費用をかけずにDIYでお家を正しくメンテナンスすることは可能です。
ただし、屋根や外壁など、足場を建てるメンテナンスは、建築会社に頼るしかなくなってしまいます。そのため、手の届かない所はなるべくメンテナンスのいらない素材を選ぶ、手の届く範囲でDIYでメンテナンスできるものを選ぶ、というのが長い目で見てメンテナンスイージーなバランスになります。
バルコニーをなくす
バルコニーは「あるのが当たり前」と思われがちですが、近年は室内干しや乾燥機の普及で用途は減少しています。
さらに10年ほどで防水メンテナンスが必要になり、掃除や鳥害対策など手間やコストがかかる点も見逃せません。
こちらも、費用を工面できず防水メンテナンスを先延ばしにした結果、雨漏りが起きてしまうという事例は多々あります。
採用するなら具体的な用途や使用頻度、維持費まで含めて本当に必要かを検討することが大切です。
さらに、高気密高断熱の家であれば、年間を通して室内の方が洗濯物がよく乾くようになるため、わざわざバルコニーに出る必要がなくなります。その場合、全く使っていないバルコニーをメンテナンスし続けないといけないという点は要注意です。
実際の住まい手の声を聞くことも選択のポイントになります。
維持管理コストをふまえて設備を選定する
住宅設備を選ぶ際は、デザインや機能だけでなく「将来の維持管理コスト」にも目を向けることが大切です。
特定メーカーしか扱えない独自仕様の設備は、交換や修理の際に高額になりやすく、言い値に従わざるを得ない状況になってしまいます。もし部品供給が終了すれば対応すら難しくなるリスクもあります。
一方で、汎用性の高い設備を選べば、顧客側が選択する権利を持つことが出来ます。複数の業者に相見積りを取り費用の比較ができたり、他メーカーにも選択肢を広げることが可能です。
長く安心して使い続けるためにも、初期の段階で「交換や修理を依頼しやすい設備」を基準にすることが賢明です。
社会資産としての家づくり

私は、家は個人の資産であると同時に社会の資産でもあると考えています。だからこそ、将来の世代に負の遺産を残さない家づくりが、私たちの責任だと思うのです。
長期優良住宅の本質を考える
長期優良住宅という制度は、単に補助金を得るための仕組みではありません。
本来の目的は、100年先も価値を持つ住宅を社会に残し、将来の日本人が住宅ローンに縛られず豊かな暮らしを送れるようにすることです。
基準をギリギリで満たすことに意味はなく、理念を理解し、次の世代も安心して住み継げる家を建てることこそが本質です。
耐久性、維持管理のしやすさ、将来の修繕計画まで含めて考えることで、住まいは「個人の資産」を超えて「社会の資産」としての役割を果たしていきます。
世代を超えて住み続ける
家づくりは自分たちの暮らしだけでなく、子や孫の世代まで影響を与える大きな決断です。
もし短命で質の低い住宅を建て続ければ、次の世代も建て替えや新築のために多額のローンを背負うことになり、負の連鎖が断ち切れません。
一方で、長く使える良質な住まいを残せば、次世代は住宅取得の重荷から解放され、より豊かな人生設計が可能になります。
だからこそ、今の家づくりには「世代を超える視点」が不可欠なのです。
空き家問題に加担しない
日本は人口減少と住宅過剰で深刻な空き家問題を抱えています。
その中で新築を建てることは、同時に空き家を一つ増やす行為にもつながります。だからこそ、これから建てる家は「ただの新築」ではなく、将来にわたって価値を保ち、社会の資産となる存在でなければなりません。
構造や素材を長持ちするものにし、修繕しやすい設計を選ぶことこそ、次の世代へ安心して引き継げる家づくりにつながります。
質の高い住まいを残すことが、次の世代や地域社会にとって本当の意味で役立つ家づくりにつながるのです。
生涯コストから考えた住宅の資金計画を

住宅を「箱」としてではなく、生涯の経済的負担を抑えつつ快適性を最大化する投資と捉えてみてください。
その考え方を基に、生涯資金計画を出せるのが、住宅性能シミュレーション兼資金計画ツール「ebfit」です。
初期費用だけでなく、光熱費や修繕費といったライフサイクルコストを「見える化」し、本当に経済的な家づくりを可能にします。
現在、「ebfit」ツール自体の一般公開は終了していますが、サイトでは住宅の生涯コストやライフプランの考え方について紹介されています。興味のある方はぜひご覧ください。
後悔のない家づくりを実現することは、ご自身の暮らしを豊かにするだけでなく、未来の社会にも価値を残すことにつながります。
最後に
今回は住宅の生涯コストについて紹介をしてきましたが、
家づくりにはまだまだたくさんの落とし穴があります。
「家づくりに失敗したなぁ」と思う人を一人でも減らせたらと思い、
ブログではとても書けない事をメルマガで発信しています。
また、メルマガに登録いただいた方には、
特別小冊子「家を建てる前に知らないと大変な事になるお金のはなし」
を特典として無料で差し上げております。
メールアドレスのみで大丈夫です。
下記フォームよりご登録くださいませ。
【実録】建築会社と担当者選びを失敗した理由