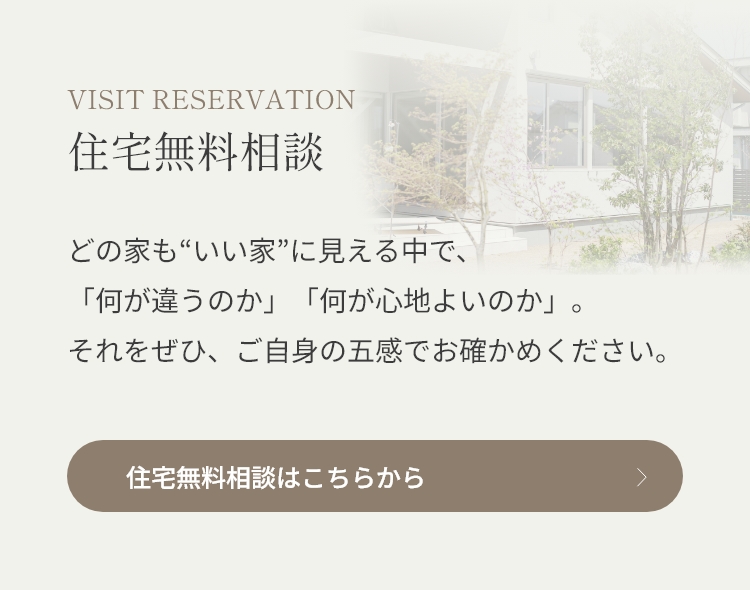QUESTION Q&A

よくある質問
- 長期優良住宅認定と性能評価認定は取得していますか?
-
長期優良住宅と建設性能評価は標準で全棟採用しております。
- 自己資金はどれくらい必要ですか?
-
設計申込の際に50万円(税抜)をお預かりします。住宅ローンを組むには自己資金が1割程度は必要だと言われますが、資金についてのご相談も無料住宅相談で承っております。
お申し込みはこちら→https://www.ohtori.net/reserve/
- 凰建設で建築した場合、構造計算の計算書を頂くことは可能でしょうか。
-
はい、可能です。構造計算や断熱計算など、全ての書類は引き渡し時に住まい手にお渡ししております。許容応力度計算の書式などは数百ページに及びますので、けっこう嵩張ります。しっかり保管していただければと思います。
- 土地は探してもらえますか?
-
ご希望であれば、不動産部門の担当が土地探しから買付けまでお手伝いさせていただきます。ご希望の土地をお探し致しますのでご相談ください。
- 打ち合わせに子供を連れて行っても大丈夫ですか?
-
キッズコーナーもご用意しておりますので、ぜひご家族でお越しください。
これまでにいただいた質問
- 凰建設では、従来法と金物工法のどちらを採用しておりますか?木造軸組み工法で従来の方法と金物工法ではやはり強度が違いますでしょうか?
-
弊社は基本的に在来工法、通し柱周りは金物工法となっております。
断面欠損はもちろん考慮するに越したことはないと思います。地震で壊れている建物は、仕口や継ぎ手が先にやられることが多いので。
- 許容応力度計算で耐震等級3の住宅は、震度7の地震に耐えた後の余震(6強などおおきな地震)が複数回来ても耐えられるのでしょうか?
-
これは私のイメージも強いのですが、耐震等級3の建物は地震が来た際でも「住み続ける」事を目的にしていると思います。潰れない事は耐震等級1でも3でも同じですが、1回の地震で各所にダメージが残り、その後住めるかどうか分からないのが耐震等級1、地震が何回来てもほぼ無傷に近く、ずっと住み続けられるのが耐震等級3という感じです。
これも震度だけでは評価しきれない部分があるので少し曖昧な返事になってしまいますが、そのようにお考えいただければと思います。
- 耐震等級3+制震で検討しています。お薦めの金物などありますか?
-
耐震等級3+制振ですね。
私も両社は必須だと思っております。
制振につきましては大きく分けて2つの考え方で商品が開発されております。商品名は色々あり過ぎますので、カテゴリ分けだけさせて頂きました。
①基本的に耐震金物だけど、許容できる力を超えたらわざと壊れて、それ以降は制振材として働くもの
②耐震性は全くないが、最初から制振材として働くもの
③その中間くらいの性能で、耐震性はギリギリカウント出来る程度のものであり、割と初期変形から制振部材として働くもの
①の物は耐震等級3を取るための構造計算に入れられることから、よく好んで使われます。②の物は構造計算上は無視されて、純粋に制振だけに効く形になります。
①の方が耐力壁としても計算できるので良いように見えますが、①の物が制振材として効くためには一定以上の負荷がかかって変形が大きくなってからになります、簡単に言うと大地震の時にだけ効くという事です。普段の細かな地震に対しては制振の建物にはなっていないという事になります。
②は地震に耐える力は一切ありませんが、わずかな地震からでも制振部材として効きますので、日常起こり得る地震で起きる内装のひび割れなどを防ぐ役割を果たしてくれています。
私としては、耐震等級3をちゃんと取ったうえで、プラスαで②の制振部材を使う方が、家の為には良いのではないかと考えております。
木造住宅で耐震等級3を取るためには、外壁面の構造用合板も内部の筋交いも必須に近いですので、特にこれでないとダメと言うものはありません。南北に長い家などは、窓面にコボットなどの鉄筋ブレース部材を使う事もあります。①が壁倍率を2倍以上取れる筋交い式の制振ダンパー材
②は壁倍率を取れない筋交い式の制振ダンパー材や車のサスペンションの様な方杖式のダンパー材、制振テープ部材が挙げられます。
③は壁倍率が1倍程度の筋交い式ダンパー材です。
- 構造体に桧は勧めていますか?
-
岐阜の地元産材に東農桧がありますので、余程の理由がない限りは東農桧を柱に使うのが基本です。
- 基礎内断熱・基礎外断熱どちらで施工されますか?シロアリ対策のため、防蟻断熱材、薬剤などの、どの様な対策を講じておりますか。ご教授ください。
-
基礎内断熱、基礎外断熱、どちらもやりますし、両方施工することもあります。基礎外断熱の場合はスタイロフォームATやパフォームガードという部材を使います。薬剤につきましては、特にこだわりはありません。
白蟻はあまり薬剤ではなく、家の作り方の方で対応していくのが良いかと思います。