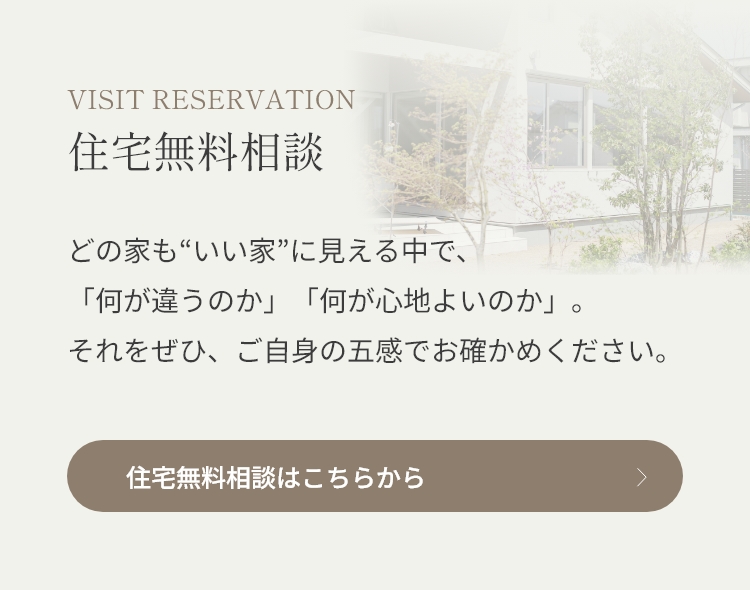QUESTION Q&A

よくある質問
- 長期優良住宅認定と性能評価認定は取得していますか?
-
長期優良住宅と建設性能評価は標準で全棟採用しております。
- 自己資金はどれくらい必要ですか?
-
設計申込の際に50万円(税抜)をお預かりします。住宅ローンを組むには自己資金が1割程度は必要だと言われますが、資金についてのご相談も無料住宅相談で承っております。
お申し込みはこちら→https://www.ohtori.net/reserve/
- 凰建設で建築した場合、構造計算の計算書を頂くことは可能でしょうか。
-
はい、可能です。構造計算や断熱計算など、全ての書類は引き渡し時に住まい手にお渡ししております。許容応力度計算の書式などは数百ページに及びますので、けっこう嵩張ります。しっかり保管していただければと思います。
- 土地は探してもらえますか?
-
ご希望であれば、不動産部門の担当が土地探しから買付けまでお手伝いさせていただきます。ご希望の土地をお探し致しますのでご相談ください。
- 打ち合わせに子供を連れて行っても大丈夫ですか?
-
キッズコーナーもご用意しておりますので、ぜひご家族でお越しください。
これまでにいただいた質問
- 白アリ対策としてホウ酸処理を床下から1mを考えています。予算次第でどこまでやってもキリがなく見える白アリ対策ですが、貴社の考え方はいかがでしょうか?
-
これもどこまでやるかはキリがありません。これは私の考え方ではありますが、シロアリ対策の基本はどこまで行っても木材の乾燥状態を保つことにあると思います。ホウ酸処理は半永久的に持つとは言われますが、木材が湿潤状態にあれば、一旦木材内に入ったシロアリは縦横に食い荒らすことが出来てしまいます。木材の乾燥状態を保つためには雨水の侵入を防ぐ事が第一です。そのためには無理なデザインをしない事です。もう一つ、木材が結露水に晒されない事です。そのためには木材部分で温度差が出来る事を避けねばなりません。木材で温度差が出来ないためには、しっかりした断熱と防湿(気密)処理が必要です。という事で、実はシンプルなデザインと高度な断熱気密は根本的なシロアリ対策には非常に有効になります。きちんと高断熱住宅に取り組み始めて以来20年、いまだにウッドデッキ以外でシロアリの被害は有りません。取り組む前の家はやはりちらほらシロアリ被害は有ります。
定期的なシロアリ薬剤処理はやるに越したことは有りません。しかし、これも建築業界の闇の一つでして、この定期的な処理で、継続的にお客様が課金してもらえる仕組みを作ったというのもまた事実です。
乾燥した木材でも食べるカンザイシロアリという種類が外国から木材と共にやってくることもあります。国産材を出来るだけ使った方が良いと言っている理由の一つが、このカンザイシロアリ対策になります。
- 依頼している工務店が基礎外断熱になります。防蟻処理された断熱材や銅板のアリ返しなどはしてもらえるのですが、何か確認しておくことなどあればお願いします。
-
私の想像ではありますが、、基礎外断熱を選択されている時点で、それなりにリスクを回避する納まりは徹底されておられると思います。
あまり口うるさく確認するのもひょっとしたら煙たがられるのではと想像してしまいますが、強いて言えば、床下の換気方法と点検の体制でしょうか。
最初の2~3年だけでも、床下の空気がしっかり動く方式をとっておられた方が無難です(会社によって給気をしたり排気をしたり、室内循環をしたり様々です)
点検については、ウッドデッキや給湯器の影など、蟻道の発見が遅れ気味な部分は何か対策をされているかどうかを確認できるといいと思います。
- 基礎外断熱について質問したいです。基礎外断熱の断熱材ではグラスウールボード、ホウ酸入り断熱材、スタイロフォームATなどが使われているようですが、耐久性や防蟻の観点からおすすめはありますでしょうか?
-
パフォームガードとスタイロフォームATを使ったことはありますが、どちらを使う場合でも、断熱材自体の防蟻については半信半疑です。
蟻返しの板金をしっかり施工するなど、断熱材がやられても良いような防蟻処理が望ましいと思います。
- 土間部分のシロアリ対策はどのように行っていらっしゃいますか?
-
基礎内断熱の場合は立ち上がりの断熱を少し薄くして熱橋と断熱のバランスを取ります。基礎外断熱の場合は、熱のバリアラインと蟻のバリアラインをそれぞれ設定して対応します。
- シロアリ対策について質問させてください。ボロンdeガードとハウスガード(緑の柱)、どちらをおすすめしますか?
-
私もどちらも使った事がありますので、どちらでも良いかと思います。
白蟻対策の基本は薬剤ではなく木材の乾燥です。そのあたりの理論理屈は京都大学の吉村教授という方が日本で最も先端の研究をされておられます。学会の理論理屈→商業バイアス→一般的な防蟻商品。という流れで世の中に普及されますが、一般的な防蟻商品の選定で迷うよりも、もっと原理原則、理論理屈に則った防蟻対策をした方が確実で安全です。
まずは木材の乾燥が大事です。それさえ100%担保できれば、防蟻材の重要性は1/10程度になっていきます。