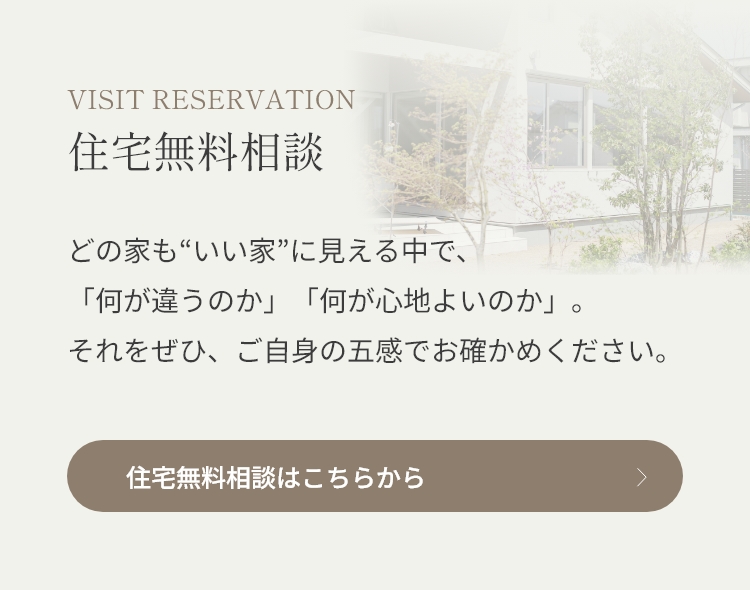QUESTION Q&A

よくある質問
- 長期優良住宅認定と性能評価認定は取得していますか?
-
長期優良住宅と建設性能評価は標準で全棟採用しております。
- 自己資金はどれくらい必要ですか?
-
設計申込の際に50万円(税抜)をお預かりします。住宅ローンを組むには自己資金が1割程度は必要だと言われますが、資金についてのご相談も無料住宅相談で承っております。
お申し込みはこちら→https://www.ohtori.net/reserve/
- 凰建設で建築した場合、構造計算の計算書を頂くことは可能でしょうか。
-
はい、可能です。構造計算や断熱計算など、全ての書類は引き渡し時に住まい手にお渡ししております。許容応力度計算の書式などは数百ページに及びますので、けっこう嵩張ります。しっかり保管していただければと思います。
- 土地は探してもらえますか?
-
ご希望であれば、不動産部門の担当が土地探しから買付けまでお手伝いさせていただきます。ご希望の土地をお探し致しますのでご相談ください。
- 打ち合わせに子供を連れて行っても大丈夫ですか?
-
キッズコーナーもご用意しておりますので、ぜひご家族でお越しください。
これまでにいただいた質問
- 廃プラやマイクロプラの問題が挙げられる中で樹脂サッシのリサイクル率に課題があることはあまり取り上げられていないように感じております。樹脂サッシ廃棄時の埋立割合を下げ、出来るだけリサイクルできるようにするには何から始めればいいと思いますか?
-
製造時の環境負荷的にも、木製>>樹脂>>>アルミだと思いますし、リサイクルの問題もまた然りですね。
全国における廃棄樹脂サッシの量は極めて少なく、リサイクルの仕組みを作るよりも燃やしたり埋めたりする方が経済的にも合理的でしたが樹脂サッシは鉱物資源の塊であり、100%リサイクルが可能な製品になります。今後増え続けるであろう樹脂サッシのリサイクル率を上げる取り組みは既に進んでおり、リサイクル樹脂の使用率を高めた商品などが今後順次発売されていきます。
リサイクル問題に対しては、まず製品の寿命をあげてやるというのが大事でして、樹脂部分が紫外線にさらされ続ける半外付け納まりではなく、内付け+付加断熱で使うなどの工夫をすることで、そもそもリサイクルに出されるスパンを長くすることが大事かなと思います。
木製サッシを使うという手法ももちろん良い事だと思います。
- LCCM取得が性能や予算面で可能な場合、取得したいと思いますか?
-
ラベリングはどちらでも良いですが、弊社では全てLCCMの取れるレベルの性能の家を建てております。
- パッシブハウス認定を取ると決めた施主様は何が決め手だったのでしょうか。コスパを考えると微妙ですが、悩んでいます。
-
勿論、認定を取るにあたり、認定費用が掛かる上に、日本のルールにおいてはそれに対して何もインセンティブが無いという事に対しては皆さん悩まれます。認定費用を断熱を分厚くすることに回したい等、様々な葛藤があります。私も、どうしても取りたいという方以外に無理にお勧めしている訳ではありません。認定を取られる方の最も大きな理由は、地球環境の為、人類の未来の為が大きいです。次いで、折角だからちゃんとしたパッシブハウスだと言いたい。という物です。この先300万円を投資しても良いと思えるのであれば、取っておいても良いかと思います。また、パッシブハウスの認定取得のチャンスは新築時だけではありません。遠い将来、大規模リフォームをされる際に、改めてパッシブハウスの認定を取るという方法もあります。(勿論今取っておいた方がトータルでは安いかと思います)
- 完成保証が付いている会社さんは失敗が少ないというイメージですが、完成保証は建築会社さん側から見て必須条件だと思いますか?
-
完成保証は失敗の有無という面もありますが、その会社の財務の健全性を測るパラメーターの一つでもあります。
小さな会社、大きな会社に関わらず、つけようと思えば完成保証を付ける事の出来る会社に頼むことが、質問者様のリスク低減につながりますので、後は自己判断ですね。完成保証を付ける事が出来る会社さんだという事を確認できれば、後は、付けるかどうかはどちらでも構いません。
- 「長期優良住宅」の「保全計画」についてなのですが、何千万円も維持管理に必要なモノでしょうか?1万円/月×30年で360万円、2万円/月なら720万円とかなりの金額に感じます。また、「保全計画」以上に長持ちして計画変更が必要な場合、その手続きは面倒なものなのでしょうか?
-
本気で100年以上家を持たせるのであれば、30年で360万円であればかなり安い方、720万円であれば妥当な所というのが実績に近い数字かなと思います。構造が長持ちして計画を変更する際の手続きは、勿論手間がかかるものにはなります。
その金額を何と比べるかだと思います。30年後に解体してもう一件家を建てるのであれば、720万円などという金額で済むはずもなく、手続きの手間や申請にかかる時間やコストもリノベのそれとは天と地ほど違います。
長期優良住宅というのは、3~4世代、住宅を住み継いでいく事を考えた時に、コストが最小になる事を考えて制度が設計されております。
その考え方に理解賛同が出来ないという事であれば、長期優良住宅は重荷になってくると考えます。