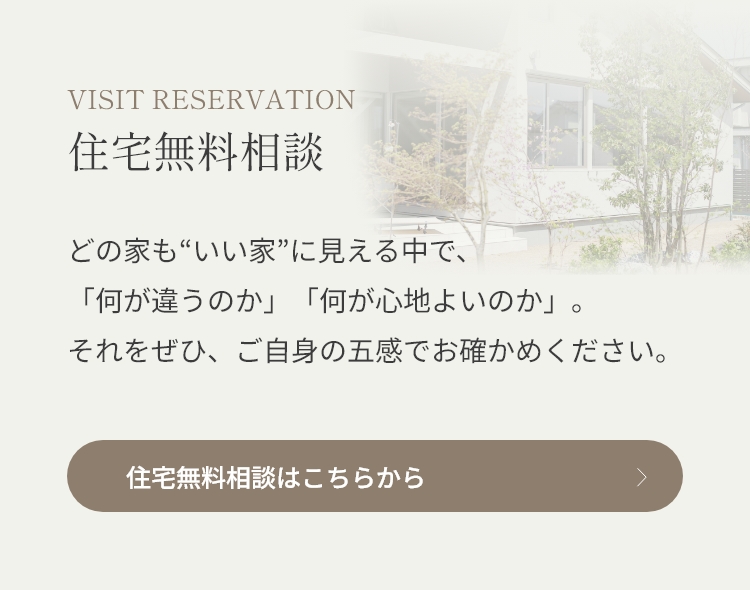QUESTION Q&A

よくある質問
- 長期優良住宅認定と性能評価認定は取得していますか?
-
長期優良住宅と建設性能評価は標準で全棟採用しております。
- 自己資金はどれくらい必要ですか?
-
設計申込の際に50万円(税抜)をお預かりします。住宅ローンを組むには自己資金が1割程度は必要だと言われますが、資金についてのご相談も無料住宅相談で承っております。
お申し込みはこちら→https://www.ohtori.net/reserve/
- 凰建設で建築した場合、構造計算の計算書を頂くことは可能でしょうか。
-
はい、可能です。構造計算や断熱計算など、全ての書類は引き渡し時に住まい手にお渡ししております。許容応力度計算の書式などは数百ページに及びますので、けっこう嵩張ります。しっかり保管していただければと思います。
- 土地は探してもらえますか?
-
ご希望であれば、不動産部門の担当が土地探しから買付けまでお手伝いさせていただきます。ご希望の土地をお探し致しますのでご相談ください。
- 打ち合わせに子供を連れて行っても大丈夫ですか?
-
キッズコーナーもご用意しておりますので、ぜひご家族でお越しください。
これまでにいただいた質問
- メルマガを拝読しているうちに、LCCM住宅への興味が湧いてきました。建材、納まり、仕様、設備、敷地選び、住まい手の維持管理など、LCCM住宅の建設にはどんなポイントがあるのか、教えていただけないでしょうか?
-
LCCM住宅は、建設から運用、解体までのトータル期間でCO2排出量がマイナスになるという住宅になります。省エネルギー性は勿論の事、生産時に発生するCO2も減らしていくことが望ましいとされます。
鉄骨やコンクリートよりは木材。木材でも集成材よりは無垢材、人工乾燥材よりは天然乾燥材を使った方が、生産工程でのCO2排出は少ないので、LCCM住宅になり易くなります。
断熱材も、出来るだけ自然由来の物を使った方が生産時のCO2排出量は少ないので、そういう物を使うと良いです。また、建設時と解体時の排出が相当なウエイトを占めますので、なるべく長い期間、建物が存続し、太陽光発電などでエネルギーを創り続けるほうが有利になります。
ポイントをまとめると、なるべく自然に近い素材で家を建てる。
なるべく省エネな家を建てる。
なるべく家を長持ちさせる。
なるべく創エネ設備を沢山つける。となるかと思います。
設備についても同じ考え方で、
長く使えるもの、メンテの容易な物を選ぶと良いかと思います。
維持管理は直接的にLCCMには関係ありませんが、
住宅の寿命を縮めるようなスパンで放っておくような事は避けていただきたいと思います。
- これからの家づくりは高耐久性、温湿度の快適性、資産性という要素が大切になると思いますが、設備についてはどうお考えでしょうか?
-
住宅を不動産としてみた時に、今までの評価であれば、どんな部位もまとめて22年で耐久性がゼロだということになっていました。
ただ、今後、既存住宅の資産評価をどのようにするのかということは各地で模索が続けられており、ある評価システムでは、基礎や躯体が60年、屋根外壁は30年、内装や設備は15年〜20年で耐用年数を考えるという提案がされています。
優れたキッチンや浴室であっても20年で資産評価はゼロだということですね。
どんな評価基準が将来の主流になるのかはわかりませんが、設備品が躯体と同じように30年を超えて評価され続けるというのは考えにくいかと思います。
「知らない人が30年使ってきた浴室」があったとして、質問者さんがそれに対してどういう印象を抱くかと考えていただければ、設備の評価が心情的にも難しいのは想像していただけるのではないかと思います。
なので、資産価値という点に関して言えば、地盤、基礎、躯体、屋根、外壁の順番にしっかりしたものに対して予算を投入し、内装やあらゆる設備品は二の次三の次というのが答えになるかと思います。
ただ、頭ではそう理解したとしても、長期優良住宅、設計/建設性能評価取得、構造計算がなされた耐震等級3、断熱等級7、だけど内装は建売とそう変わらない。という家をどのくらいの人が受け入れられるのか、というと、なかなか難しいですよね。
- 手刻みの伝統工法の保存、継承についてどのようにお考えですか?
-
現段階で弊社は手刻みの伝統工法の保存、継承については比較的積極的に取り組んでいる状態です。毎年弊社の社員大工が数名、刻み技術の全国技能競技会に出場致します。
ただ、今後はどうかとなりますと、残念ながら仕事の必須スキルとしての継承は難しいと考えております。これは大工技術に限らず、すべての伝統的な技術は次第に機械がその担いをすることになってくるからです。昔は飛脚など走る事が職業になった時代もありましたが、現代では走ることはスポーツなどのレクリエーションの一環です。
弊社のある岐阜県では「鵜飼い漁」が有名ですが、昔は生活の糧を得るための一つの仕事であったのが、今は宮内庁が無形文化財として保護する観光資源です。
同様にカンナで木材の表面を美しく仕上げる技術も最近ではほぼ機械が行い、「削ろう会」などの有志の方が、本業と趣味の境界があいまいな中でなんとか技術の継承を行っている状態です。
今後、個人住宅の業界においては、伝統工法への回帰よりも、さらなるプレカット化、ユニット化が進みます。この流れの最も大きな要因は、人手不足による労働力を補う為です。
手刻みの伝統工法の技術継承は普段の仕事を通してではなく、20年おきに行われる伊勢神宮の式年遷宮などの行事により、担われていく事は想像に難くありません。
返答をまとめますと、伝統工法の保存継承は大切な事であると位置づけてはおりますが、仕事の必須スキルとしてとは考えておりません。
- 注文住宅で設計士がプラン前に建築現場の周辺などを目視で確認するのは必須ですか?グーグルマップでも良いですか?そしてそれは工務店選びの重要なポイントでしょうか。
-
最近では土地を見なくても設計が出来る状況が整ってしまっておりますが、やっぱりできれば土地は見たほうが良いかと思います。
土地を見に行くかどうかは家づくりが好きかどうかじゃないでしょうか。
- ZEH住宅の対応可能ですか?
-
ZEHも勿論対応しております。今の所弊社のZEH率は85%程度です。