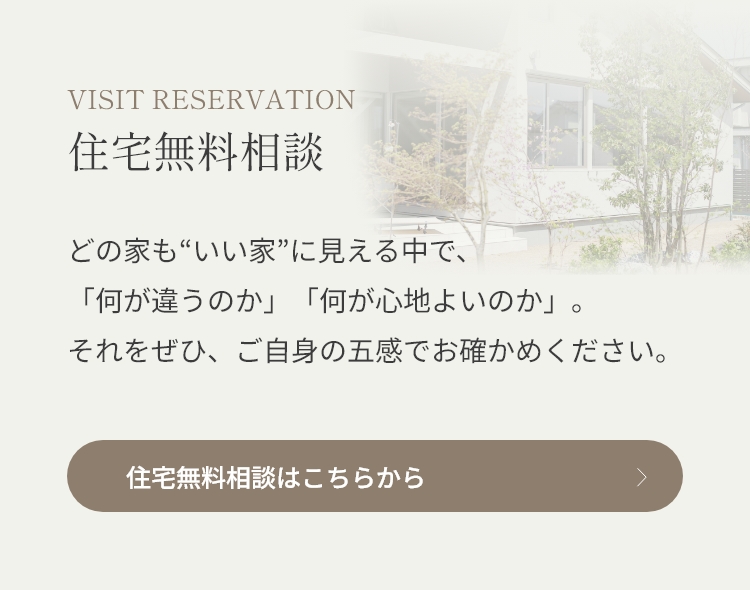QUESTION Q&A

よくある質問
- 長期優良住宅認定と性能評価認定は取得していますか?
-
長期優良住宅と建設性能評価は標準で全棟採用しております。
- 自己資金はどれくらい必要ですか?
-
設計申込の際に50万円(税抜)をお預かりします。住宅ローンを組むには自己資金が1割程度は必要だと言われますが、資金についてのご相談も無料住宅相談で承っております。
お申し込みはこちら→https://www.ohtori.net/reserve/
- 凰建設で建築した場合、構造計算の計算書を頂くことは可能でしょうか。
-
はい、可能です。構造計算や断熱計算など、全ての書類は引き渡し時に住まい手にお渡ししております。許容応力度計算の書式などは数百ページに及びますので、けっこう嵩張ります。しっかり保管していただければと思います。
- 土地は探してもらえますか?
-
ご希望であれば、不動産部門の担当が土地探しから買付けまでお手伝いさせていただきます。ご希望の土地をお探し致しますのでご相談ください。
- 打ち合わせに子供を連れて行っても大丈夫ですか?
-
キッズコーナーもご用意しておりますので、ぜひご家族でお越しください。
これまでにいただいた質問
- 窓の日射遮蔽の方法について質問です。これから新築する我が家は、6地域でHEAT20のG2くらいの仕様かつ東道路、南は隣家と3mほど空いています。夏の日射遮蔽にすだれを使おうと思っているのですが、二階の南窓・東窓は滑り出し窓ですだれやシェードがとりつきません。窓の大きさは700×900で南は少し軒が出ています。どうやって日射遮蔽するのがいいのでしょうか?
-
南は軒をなるべく出す、東西は窓をなるべく減らすというのが、2階の日射遮蔽は有効です(角度があまり振れていない場合)
それができないのであれば、せめて反射率の高いカーテンなどを取り付ける事になりますが、内側で出来る日射遮蔽対策は大して効果はありませんので、気休めくらいに思ってください。
- 可変調湿気密シートの長期耐久性ってどうなのでしょうか?そもそも、気密シート無しでも内部結露しない壁構成が必須のように思えるのですが。
-
こちらは、私も同様の問題意識は持っておりますが、現状では分からないというのが正直なところです。一般的に物質の劣化原因は、熱、水、紫外線になりますが、そのうちの熱と紫外線から守られているのが気密シートの施工位置になります。残りの、水による劣化がどの程度なのかは耐久性試験の結果からも分かりにくい商品が多く、ひょっとするとやはり30年に1度はめくらないとダメな物かもしれません。
- 壁内の結露、カビ対策について伺いたいです。冬は室内からの湿気を壁内に入れないようしっかり気密をとるのが基本だと思いますが、夏に関してはどうすればいいのでしょうか?夏は外の方が湿度が高いのでエアコンにより室内が冷やされた場合、壁内で一番室内に近い部分が結露してしまうのでないか心配しています。
-
夏型結露の心配ですね。心配されるお気持ちは大変理解できます。理論上、夏型結露は発生し得るものですから。
例えば、夕立が有ったりすると、コンビニの窓ガラスが曇ったりします。車の運転中、冷房をダッシュボードから吹き出す設定にすると、フロントガラスの外側が結露を起こします。
これが生活するうえで身近に起こる夏型結露ですね。では、これが家の壁の中で起こりえるのかどうかという事について考えてみたいと思います。
夏の冷房時の室内温度が例えば26℃だとします。壁内で一番室内に近い側が、そのまま26℃になったと考えますと、その時の飽和水蒸気量は21.35g/kgです。この、21.35g/kgという水蒸気量になるタイミングは、一年でどのくらいあるのかという話ですが、2019年の岐阜県岐阜市の夏の実績ですと、8/16の午前10時から正午までの2時間だけ、この値を超えております。
夏は湿気が高いのは事実なのですが、住宅で常識の範囲内でエアコンの温度設定をして生活をしている限りでは、壁体内の夏型結露というのはそんなに発生しないというのが答えになります。結露を起こすかどうかは、絶対湿度に対して露点温度を下回れば結露するという単純な物理の話です。
夏の結露でもっと心配なのは、明け方の放射冷却によっておこる自然結露です。草に朝露が付いたり、朝靄が発生したりというのもこの現象が手伝っております。
住宅で言えば、屋根の裏側などでこのような現象が起こる可能性があります。これを防ぐためにはやっぱり家に断熱を施し、家中のあらゆる箇所がどんな季節でも露点温度以下にならないようにするというのが最も効果的な対策になります。
調湿気密シートを使ったりという対策もよくなされますが、そんなことよりも、真っ向から断熱に取り組むほうが先です。ヨーロッパ北米並みの断熱をして初めて、調湿気密シートを考え始めましょう。
- メンテナンスを考えた際、貴社では屋根のルーフィングはどのような提案をされますか?またそれによるコスト増はどうなりますでしょうか?
-
基本的にゴムアスファルト系の物を勧めておりますが、これも屋根材との相性によって変わってきます。
ルーフィングそのものも大事ですが、合板の下に風を通す事も非常に大事で、色々な要素が複合されてきますので、建物の計画によるとしか言えません。
良い物を使えば当然コストは上がりますが、屋根材を一度葺き替えることに比べれば、全く大した金額ではありません。
- 配線の耐久性について質問です。配線の安全性を重視するとおおよそ何年後くらいに交換が必要になりますか?また、配線のメンテナンス性を考えた場合、どのような設計をすればいいでしょうか?
-
電線の直線部分でトラブルが起きる可能性はそこまで高くなく、どちらかというと結束部分です。
断熱材や配線をすべて交換する作業は、新築と同等の作業になり費用も建て替えよりちょっと安い程度の大規模なメンテナンスになってしまいますので、お勧めしておりません。
そのため、断熱材も電線もそのまま埋め殺して、室内にもう一層、配線層を作るというのが落としどころだと考えております。