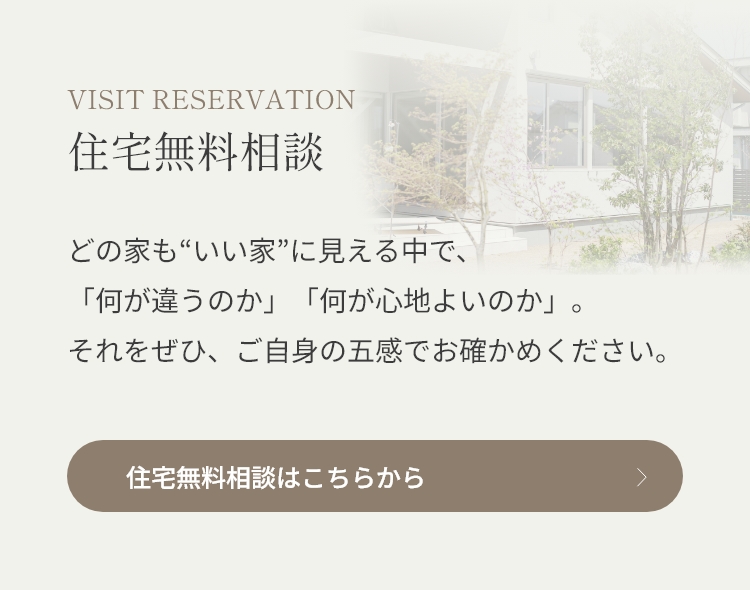QUESTION Q&A

よくある質問
- 長期優良住宅認定と性能評価認定は取得していますか?
-
長期優良住宅と建設性能評価は標準で全棟採用しております。
- 自己資金はどれくらい必要ですか?
-
設計申込の際に50万円(税抜)をお預かりします。住宅ローンを組むには自己資金が1割程度は必要だと言われますが、資金についてのご相談も無料住宅相談で承っております。
お申し込みはこちら→https://www.ohtori.net/reserve/
- 凰建設で建築した場合、構造計算の計算書を頂くことは可能でしょうか。
-
はい、可能です。構造計算や断熱計算など、全ての書類は引き渡し時に住まい手にお渡ししております。許容応力度計算の書式などは数百ページに及びますので、けっこう嵩張ります。しっかり保管していただければと思います。
- 土地は探してもらえますか?
-
ご希望であれば、不動産部門の担当が土地探しから買付けまでお手伝いさせていただきます。ご希望の土地をお探し致しますのでご相談ください。
- 打ち合わせに子供を連れて行っても大丈夫ですか?
-
キッズコーナーもご用意しておりますので、ぜひご家族でお越しください。
これまでにいただいた質問
- 洗面脱衣室の床材はどのようなものがオススメでしょうか?無垢材を使うことは劣化のリスクが高いでしょうか。
-
私の自宅は厚さ40mm程の杉の無垢床、無塗装材を使っております。夏はさらさら、冬はひやっとせずに快適です。水が溜まったまま放置という状況が続くと良くないですが、あまり気にせず使っております。当然水染みなどはありますが、劣化しているという感じにはなりません。そういう事も含めて表情が変わっていく家を慈しむことができるのであれば、針葉樹の無垢床は大変お勧めになります。
それが嫌であれば、水の浸みにくい素材が無難かと思います。
- キッチンにコルクの床材を使うのは、費用対効果の点でどうでしょうか?
-
コルクは木材の中では水に強く、感触も柔らかい為、水回りの素材として重宝されてきました。しかし、水に強くて柔らかいという性質だけでしたら、コルク柄のクッションフロアの方が上ですし費用対効果も高いです。
コルクを使う意味は、本物の持つ木目を求めるとか、長期的な耐久性をクッションフロアよりは求めるとか、そういう意味合いになるかと思います。基本的にコルクの床は作り方としてはベニヤやOSBなどと同じで、木材を接着剤で固めたものになりますので、無垢の床よりは紫外線などでの劣化は早い(接着剤成分がどうしても)です。
- 我が家の外壁はパワーボードで塗料はグランロックです。サイディング同様、塗り替えは必要ですが外壁自体は長持ちすると言われています。森さんはパワーボードについてどのようにお考えでしょうか?
-
パワーボードはサイディングに比べると非常に耐久性のある外装材になります。多少塗り替えをサボったとしても頑丈に家を守ってくれますので、私はありだと思っております。ただ、ガルバと同じように、テクスチャの種類は限られますので、デザインの種類はそれほど多くないですね。
パワーボードで、裏に通気層がしっかり取ってある建物は、夏の暑さのピークをシフトしてくれますので、高断熱住宅との相性も悪くないと思います。
- 機能やデザインを含めておススメの照明はありますか?また、選ぶ際に気を付けることなどあれば教えてもらいたいです。
-
多分誰に聞いても返ってくる鉄板の答えとしては青山製陶のソケット+裸LED電球の照明をブラケットに使うという物ですね。それを多用して浮いたお金で、これぞというダイニング上のペンダントを選ぶのが、いい感じかと思います。
選ぶ際に気を付けることは、自分の好みを設計士さんにはっきりと伝える事です。照明器具は性能部材です。光量や範囲等ある程度計算も必要です。自分で選んでもダメではありませんが、細かい器具の選定は設計士さんに任せたほうが確実だと思います。
- トイレは立って行いますが、クッションフロアだと少し安っぽく見えてしまいます。耐久性他でクッションフロアもオススメなのでしょうか?
-
立ってされる場合は「イージーメンテナンス」を目指すか「ノーメンテナンス」を目指すかになります。イージーメンテナンスは、交換が簡単にできるようにしておくことで、クッションフロアなど、交換が容易で安いものにしておくイメージです。ノーメンテナンスを目指す場合は、目地の少なく耐久性の高いものを床材にすることです。TOTOのハイドロセラフロアやタカラのホーローフロアなどが該当するかと思います。
キッチンは、リビングの床材をそのまま貼っても大丈夫です。タイルは見た目も良いですが、目地部分は無垢材のフローリングと同じように染み込みますので目地のないフロアタイルでも気をつけたいですね。
お金をかけるか、掃除の手間をかけるか、生活の在り方を変えるか、仕方ないと諦めるか、どれか一つを選ぶのではなく、どの程度の割合で大事にしたいかを考えて自分の価値観を把握されると良いと思います。