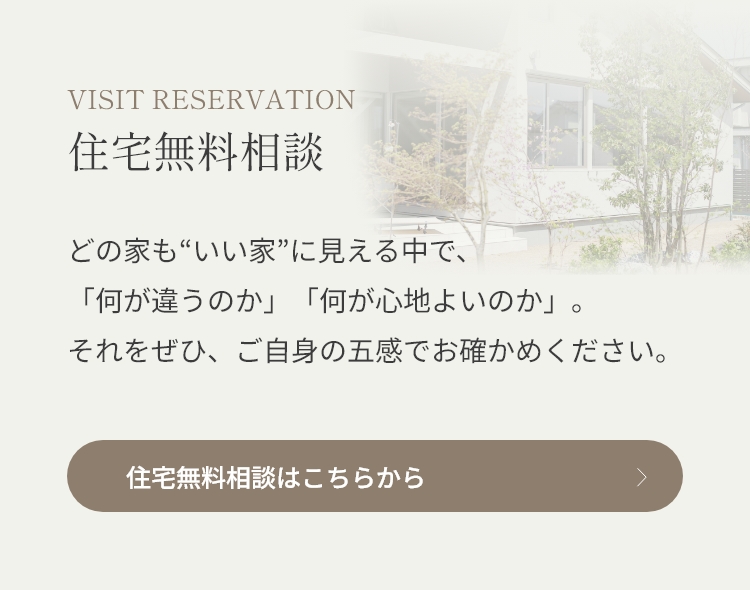QUESTION Q&A

よくある質問
- 長期優良住宅認定と性能評価認定は取得していますか?
-
長期優良住宅と建設性能評価は標準で全棟採用しております。
- 自己資金はどれくらい必要ですか?
-
設計申込の際に50万円(税抜)をお預かりします。住宅ローンを組むには自己資金が1割程度は必要だと言われますが、資金についてのご相談も無料住宅相談で承っております。
お申し込みはこちら→https://www.ohtori.net/reserve/
- 凰建設で建築した場合、構造計算の計算書を頂くことは可能でしょうか。
-
はい、可能です。構造計算や断熱計算など、全ての書類は引き渡し時に住まい手にお渡ししております。許容応力度計算の書式などは数百ページに及びますので、けっこう嵩張ります。しっかり保管していただければと思います。
- 土地は探してもらえますか?
-
ご希望であれば、不動産部門の担当が土地探しから買付けまでお手伝いさせていただきます。ご希望の土地をお探し致しますのでご相談ください。
- 打ち合わせに子供を連れて行っても大丈夫ですか?
-
キッズコーナーもご用意しておりますので、ぜひご家族でお越しください。
これまでにいただいた質問
- 配線寿命の動画から質問です。配線スペースを確保した家で実際に配線交換する場合、どのように行うのでしょうか?
-
配線交換の頻度は30~40年に一回を想定しています。その工事を行うのは、自分ではなく次の世代の人になるかと思います。その際はいったん断熱気密処理が終わった状態にまで内装を剥がし、電線もやり直しつつ内装をやり直すイメージです。一部屋ずつでも良いかと思います。壁を剥がさないで電線をやるのであれば、全ての電線を配管に入れておくと良いかと思いますが、木造の建物であれば、プラスターボードを剥がすところまでならさほどの手間でもないので、前者のやり方でも良いかと思います。
- 今後の夏型結露を考えると難しいところではあると思いますが、通常の防湿シート(ポリシート)だと夏型結露には不利ですよね?充填断熱でネオマフォームやフェノバフォームやウレタンフォームなどで問題はありますか?
-
可変調湿シートの耐久性は、何とも言えませんが、家の中の環境で使う物ですので、外部のものほどは気にしなくても良いのではと思っております。有利不利は、壁体構成によりますので一概には言えません。ネオマやフェノバを100mm施工するよりも、防湿フィルムの方が透湿抵抗は高いですので、十分に分厚い外皮を設計し、地域の気象条件や内部の使用環境に応じた位置に防湿フィルムを施工することで、可変タイプではなくとも夏冬の壁体内結露を防ぐことは可能です。どちらかというと、素材の特性よりも設計や施工の慣れの方が大きいと思いますので、それぞれの建築会社さん、設計士さん、大工さんが得意な方法で、しっかりと対策していただけるのが良いかと思います。
- なぜJIS規格では、透湿防水シート(A・B)と透湿ルーフィングで基準となる透湿抵抗が違うのでしょうか?外壁と屋根で求められる透湿性が違うのか、あるいはそれぞれの商品(メーカー)の棲み分けとなるよう基準設定されているのでしょうか?
-
屋根のルーフィングは施工中において人が歩くことを想定しておりますので強度が必要となります。強度を増すためには分厚くする必要がありますが、そうすると透湿抵抗値はどうしても高くなり、湿気を通しにくくなります。本当は透湿抵抗値は低い方が安全側に働くはずなのですが、強度と透湿性のバランスを求めた結果現在の数字になっているようです。
- 木材の腐朽要因として含水率がありますが、表面からどこまでの厚みの平均を測定できるかは、(特に非破壊の)水分計によっては様々だと思います。これといった厚みの目安はあるのでしょうか?
-
一般的に住宅用の木材は構造材で厚みが105mm~120mm程度あります。そのため、測定深度が50mm程度の物であれば、大概の材料の含水率は適正に測れると思ってよいかと思います。
5万円程度の高周波式含水率計であれば、その程度は測れるかと思います。
- 結露について質問です。防湿ラインを断熱材の室内側できっちり取る、面材は透湿抵抗の小さいものを選定するなどし、壁内結露対策は出来ていたと仮定します。その上で、家の一角にグラスウール300mm(防湿シートなし)の壁で包まれた防音室が出来た場合、防音室と外壁の間で結露のリスクは高くなりますでしょうか?
-
グラスウールは防音の為だとするのであれば、300mmグラスウールと、外壁構造の防湿ラインの間に、通気層を作ってあげればよいかと思います。300mmのグラスウールを断熱の足しにもしたいという事であれば、防湿ラインを丁度いい所を計算して300mmの厚みのどこかで取られるようにすると良いかと思います。
断熱気密防湿をきちんと計算してくれる会社さんであれば、そこまで難しい注文ではないかと思いますので、依頼先にそのまま相談されると良いかと思います。