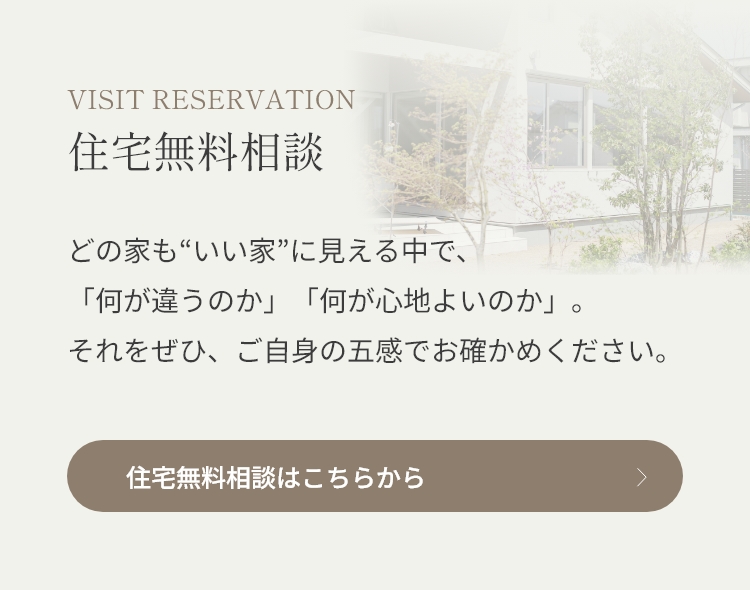QUESTION Q&A

よくある質問
- 長期優良住宅認定と性能評価認定は取得していますか?
-
長期優良住宅と建設性能評価は標準で全棟採用しております。
- 自己資金はどれくらい必要ですか?
-
設計申込の際に50万円(税抜)をお預かりします。住宅ローンを組むには自己資金が1割程度は必要だと言われますが、資金についてのご相談も無料住宅相談で承っております。
お申し込みはこちら→https://www.ohtori.net/reserve/
- 凰建設で建築した場合、構造計算の計算書を頂くことは可能でしょうか。
-
はい、可能です。構造計算や断熱計算など、全ての書類は引き渡し時に住まい手にお渡ししております。許容応力度計算の書式などは数百ページに及びますので、けっこう嵩張ります。しっかり保管していただければと思います。
- 土地は探してもらえますか?
-
ご希望であれば、不動産部門の担当が土地探しから買付けまでお手伝いさせていただきます。ご希望の土地をお探し致しますのでご相談ください。
- 打ち合わせに子供を連れて行っても大丈夫ですか?
-
キッズコーナーもご用意しておりますので、ぜひご家族でお越しください。
これまでにいただいた質問
- 基礎断熱で、床下エアコン等の床下を温める手法を取らない場合、床は冷たくなってしまうでしょうか?絨毯などはあまり使用せず、無垢床を素足で過ごすのが夢なのですが。断熱性はG2程度を想定しています。
-
引っ越した当初に寒さを感じる事は無いと思います。恐らく足元環境も含めて今までよりもはるかに暖かい環境が手に入るはずです。
ただ、床下に熱源のある家と比べてしまうと、暖かさの差は次第にはっきり感じ取れるようになっていきます。人間のセンサーが敏感になってくるからです。床下に熱源の無い家の場合、床の冷たさを決めるのは気密性と窓からのコールドドラフトになります。エルスターXやAPW430(→樹脂サッシ)を使ったG2とエピソードやサーモスⅡH(→アルミ樹脂複合サッシ)を使ったG2では足元の暖かさは全然違うという事です。
人間の足の冷たさセンサーは引っ越し以降どんどん繊細になっていきますので、2年目、3年目と住むにつれて、なんだか寒くなってきたという感想を抱かれるかもしれません。
- UA値0.34の家でも0.30の家でも、仮に両者の計算上の冷暖房費が同じなら、快適性も同じなのかと思っていたのですが、体感温度は室温だけではなく、周囲の表面温度で決まるという事を知りました。その事を考慮した場合、連暖房費が同じでもUA値0.30の家の方が体感温度的に快適になりますか?
-
仰る通り、UA値が下がれば下がるほど、家の中の環境は快適になります。一般的に家全体を暖める暖房方式の場合、住宅の中央部分ほど快適性が高く、窓や外壁に近づくほど不快感が高まります。
中央部分は部屋の室温もその周りの間仕切り壁も家の中で最も高い温度になっております。逆に窓周りなどは家の中でも最も低い温度になっております。この温度差が体感温度を下げる原因になります。UA値が下がるほどに窓の部分や外壁部分の温度低下度合いが下がりますので、家中の温度が均一に感じられやすいという仕組みになります。
余談ではありますが、窓の性能がものすごく高い物を使い、壁の断熱が程々のUA値0.34の家と、壁がものすごく性能が良くて、窓の性能が程々のUA値0.30の家を比べると、0.34の家の方が暖かく感じるという事が起こり得ます。この場合はUA値0.34の家の方が家中満遍なく同じ温度になり、UA値0.30の家は窓の周囲だけ極端に冷えますので、温度ムラが大きいという意味で、0.30の家の方が寒く感じられるという事になります。
UA値を上げる目的は、光熱費を抑えるという事もありますが、家の中の環境を穏やかで優しいものにするためという意味合いも大きいです。是非、UA値が0.87の家から0.20くらいの家までを真夏や真冬に体感して違いを感じてみて下さい。
- いつもメルマガで勉強させて頂いています。芥見南山パッシブハウスなど、窓や扉は比較的凡庸なものなのに、高い性能で驚きます。やはり、まずは壁や屋根の断熱、と考えるのが正解ということでしょうか。
-
芥見南山パッシブハウスの窓や扉ですが、Uw値が0.8前後と、国産の最上位窓と同じかそれ以上の性能の物を使っております。決して窓を疎かにしているわけではありません。
ちなみに日本の一般的なアルミペアガラス窓は4.66になりますので5倍の性能という事になります。
グラスウールを申し訳程度に入れた壁で同じく壁のU値が0.8程度になります。
南山パッシブハウスの壁のU値は0.15程度です。という事を前提にお話しますが、一般的に家の外皮における窓面積の割合というのは5%前後になります。外皮の断熱性能を表すUA値は、全ての断熱構造の平均値になります。今までは壁の断熱性能に比べ、窓の性能が1/5くらいしかなかったので、5%程度の面積の窓から入ってくる熱が家全体の3割以上になり無視できない値になりましたが、十分に性能の高い窓は、家の性能にそこまで影響することはありません。少しずるい話になりますが、窓が全くない家を設計しますと、グラスウール100mm程度の断熱でもUA値が0.4を下回り、G2グレードの家になります。
順番的には、まず窓の性能をUw値1.5以下の物(LIXILのエルスターSやYKKのAPW330相当)にする事、そのあとは窓よりも屋根や壁を中心にU値0.2以下(グラスウールで200mm)を目指す。両方超えたらまた窓をUw値1.0以下の物に変えていくというのが今のところの順番ではなかろうかと思います。
家の性能向上はボトルネックをつぶしていく作業です。高性能な家のどこかに大きなボトルネックがあると、痛みがそこに集中するからです。
また、パッシブハウスクラスまで行きますと、既製品の窓の性能限界が来てしまいますので、後は壁や屋根で性能を上げていくしか方法がないというのもあります。
- 床断熱+天井断熱の家と、基礎断熱+屋根断熱の家だと気積が結構違うと思います。温熱環境の面で気積の大小による有利・不利などありますでしょうか?
-
非常に鋭い質問ですね。おっしゃるように、基礎/床、天井/屋根で気積が変わってきますので、例えばC値を測定する時の分母が変わってきたり、UA値を計算する時の外皮面積が変わってきたりします。一般的には分母が大きくなればなるほど、係数は下がりますので、床断熱+天井断熱の家よりも、基礎断熱+屋根断熱の家の方が、UA値やC値は下がりやすいです。ただ、それらの係数は下がっても、隙間の絶対値や、熱が逃げる外皮の絶対的な面積は増えておりますので、光熱費は基礎断熱や屋根断熱の方が増える事になります。
屋根断熱をするのであれば、小屋裏空間を上手に使って、勾配天井や、ロフト部屋を有効活用しないと勿体ない事になってしまいます。
参考にしていただければと思います。
- 屋根断熱をする際に、ダンボール製の通気部材にアイシネンを吹き付けするのは通気層の確保に問題ないでしょうか?また、基礎内断熱の断熱材として基礎部分に直接アイシネンを吹き付けるのは長期的な性能維持も含めて問題ないでしょうか?
-
屋根に関してはよく行われるやり方ですね。
施工する職人さんの匙加減で段ボールが通気層側にどれだけ膨らむかが決まりますので、これは職人さんによるというのが答えになります。
基礎についてですが、こちらもよく見かける気がしますが、形状が単純である基礎は、ボード状の断熱材を施工した方が厚みの確保や断熱材の質の確保もしやすいと思いますので、わざわざ現場吹付を行わない方が良いのではと思ってしまいます。
長期的な性能も問題かもしれませんが、基礎の場合は防湿フィルムの施工がなされない例が殆どですので、湿気の出入りは有りますね。